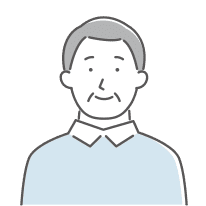相続とは
相続とは、亡くなった方の預貯金、不動産、株式などの資産を配偶者や子どもなどの親族が引き継ぐことを言います。
相続では亡くなった人のことを「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」と言います。
一般的には配偶者や子どもなどの家族が財産を引き継ぎますが、現在の法律では遺言状を作成することで家族以外に財産を分けることも可能です。
詳しくは後述しますが、相続人はどこまでが含まれるのか、相続の範囲となる財産はどこまでなのか、相続を実現するためにはどのような手順で何に気を付けて行えばよいのか、といった点に注意が必要です。
相続の手続きについて
ここでは相続の手続きについて解説します。全体の流れは下記のとおりです。
1. 死亡届の提出
2. 遺言書の確認
3. 相続人の確定
4. 相続財産を把握
5. 相続放棄、限定承認
6. 準確定申告
7. 遺産分割協議書の作成
8. 名義変更等の手続き
9. 相続税申告
10. 遺留分減殺請求
まずは死亡届を提出し、遺言状の確認や相続人の確定の後、遺産分割協議書に押印します、その後、各種名義変更等を行い、相続税の申告をすることになります。
各項目について以下で詳しく見ていきましょう。
1. 死亡届の提出
人が亡くなると、医師から家族へ死亡診断書が渡されます。
死亡診断書は死亡届と一体になっており、左側が死亡届、右側が死亡診断書となっています。
死亡届に必要事項を書く欄があるので、1つずつ書いていきましょう。
書き終えたら市役所に提出することになります。
死亡届は何度も使うことになるので提出前にコピーを5部程度とっておくと良いでしょう。
また、死亡届は死後7日以内に提出する必要があるで、死亡後はできるだけ速やかに提出します。
死亡届を提出する際は、同時に火埋葬許可申請書を提出します。
これにより火葬許可証が手に入るので、葬儀社に持っていくことで火葬の手続きを進めることができます。
2. 遺言書の確認
死亡届を提出したら、次に遺言書を確認する必要があります。
一般的には配偶者や子どもなどの家族が相続人となりますが、遺言書があればそこに書いてある内容で相続人が決まります。
故人の遺言書がないか、机の引き出しやタンスの中などいろいろな場所を探しましょう。
ここで気をつけるべきは、遺言書を見つけてもすぐに開封してはいけないという点です。
遺言書を見つけた場合、亡くなられた方の住所を管轄している家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があります。
これをせずに遺言書をすぐに開封してしまうと、5万円以下の過料を払わなくてはなりません。
3. 相続人の確定
遺言書がある場合は、遺言書に記載されている人が相続人になります。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を協議する必要があります。
遺言書がない場合の相続人選定については、まず配偶者と子ども、次に死亡した人の直系尊属である父母など、その次に死亡した人の兄弟姉妹が該当します。
これは除籍謄本や改製原戸籍謄本を元に調査され、民法に基づき相続人が確定されます。
4. 相続財産を把握
次に、相続財産を計算します。
相続財産とは相続の対象となる財産全てのことを指します。
具体的には、預貯金や株式、不動産、自動車、貴金属が該当します。
故人が借金をしていた場合、その借金も負担する必要があることに注意が必要です。
相続財産を把握した結果、財産がマイナスであった場合は、次に挙げる相続放棄や限定承認を行うことで、借金を回避することができます。
5. 相続放棄、限定承認
「相続放棄」とは、プラスの財産とマイナスの財産の両方を放棄することです。
相続放棄を行うと預貯金などの財産を受け取ることはできなくなりますが、故人が負っていた借金などのマイナスの財産も相続せずに済みます。
一方「限定承認」とは、相続財産の内容を見て、支払う必要のある借金などの負債を全て支払った後に残金があった場合に相続する手続きです。
一見メリットしかないようにも思いますが、時間がかかる点や、相続人の全員で行わなければいけないという点がデメリットです。
相続放棄や限定承認の手続きには期限があり、「自分のために相続があったと知ったときから3ヶ月以内」と定められています。
3ヶ月という短い期間なので、相続財産に借金があると分かり次第、相続放棄するのか限定承認するのか、あるいは単純承認するのかを、なるべく早く決める必要があります。
6. 準確定申告
故人に所得があった場合、相続人が代わりに確定申告を行う必要があります。
このように確定申告を代わりに行うことを「準確定申告」と言います。
特に、故人が事業をしていたり2,000万円以上の所得があったりする場合には準確定申告を行う必要があります。
準確定申告の期限は故人が死亡してから4ヶ月以内です。
期限を過ぎると延滞税がかかる可能性があるので注意しましょう。
7. 遺産分割協議書の作成
続いて遺産分割に進みます。
相続財産を把握した後は、相続人同士で遺産を分割するための協議をする必要があります。
これを「遺産分割協議」と言います。
相続人が一堂に会する必要はなく、メールや電話などを通じて協議をしても構いません。
協議がまとまったら、その内容を証明する「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書には相続人の全ての印鑑が必要になります。
遺産分割協議が上手くまとまらない、もしくは一部の相続人が協議に参加しようとしない場合は、家庭裁判所で「遺産分割調停」をすることもできます。
家庭裁判所の調停員が間に入って、遺産分割について話し合いを進めることができます。
この調停でも意見がまとまらない場合、いわゆる裁判である「遺産分割審判」を行うことになります。
8. 名義変更等の手続き
遺産分割協議書の作成が終わり、遺産の分配について決定した後、故人の遺産の名義変更の手続を行います。
具体的には、預貯金や有価証券、不動産や自動車、ゴルフ会員権、電話加入権、損害保険など、故人の各遺産について名義を変更します。
管理している組織団体は当然異なるため、それぞれの手続きを個別に行わなくてはなりません。
別々の場所に出向いての手続きも必要になるため、多くの労力がかかります。
9. 相続税申告
各種名義変更などの手続きを終えると、実際に引き継いだ遺産の金額を元に、相続税を支払うか支払わないかの判定をします。
遺産総額から「基礎控除額」を差し引いた金額が1円でもあれば、相続税が発生することになります。
基礎控除額は「3,000万円+法定相続人の数✕600万円」で算出できるので、仮に相続人が3名の場合は、遺産総額が4,800万円以下であれば相続税はかからず相続税申告も必要ないということになります。
ただし遺産総額が基礎控除額を超えたとしても、様々な控除や特例制度があるため、一度税務署や近くの税理士に相談してみることをお勧めします。
相続税の申告書は、相続人全員が共同して作成し、税務署に提出するパターンが一般的です。
自分たちで申告書を作成することもできますが、申告漏れや計算ミスなどをする恐れがあります。
万が一漏れや間違いがあるとペナルティとして加算税がとられてしまうため、税理士などの専門家に代行して申告書を作成してもらうと良いでしょう。
10. 遺留分減殺請求
遺産相続には「遺留分」という考え方があります。
遺留分は一定範囲内の相続人における遺産の最低取得可能分のことで、取得できる最低限の遺産の量を意味します。
「遺留分減殺請求」とは、この遺留分を侵害された時に、遺留分の取り戻しを請求するための手続きのことです。
例えば、遺言書に「全ての遺産を愛人に渡します」と書いてあった場合でも、相続人が配偶者のみの場合であれば、配偶者は遺留分として遺産の1/2を受け取る権利があります。
そのため、愛人に対して遺留分減殺請求をして、遺産の1/2を渡すよう請求することができます。
遺留分減殺請求の期限は、被相続人の死亡と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内となっています。
遺留分を侵害されている場合は早めに遺留分減殺請求を行いましょう。
困ったら専門家に相談を
今までご説明したように、相続についての手続きは多くのステップがあり、期限や方法など気をつけなければいけない点が多々あります。
困ったことや疑問が生じたら、弁護士・司法書士・税理士・行政書士などの専門家に相談すると良いでしょう。
各専門家は依頼できる範囲や得意分野が異なります。
遺産相続について争いがある時は弁護士、相続財産に不動産がある場合は司法書士、相続税申告がある場合は税理士という具合に、専門家を事前に調べてから相談すると良いでしょう。
まとめ
この記事では相続の概要と全体の流れについて解説しました。
相続は「残った財産を子どもか配偶者が引き継ぐもの」と単純に考えていた方も少なくないかと思いますが、実際には、誰が相続するのか、相続するものはマイナスのものも含めてどれくらいあるのかを確認することから始めなくてはなりません。
踏まねばならない手順が多く、それぞれに明確な期限も定められています。
多くの場合葬儀の手配と並行して行うことになるため、自分で無理して全て行おうとせず、状況に応じて専門家に任せることをお勧めします。
























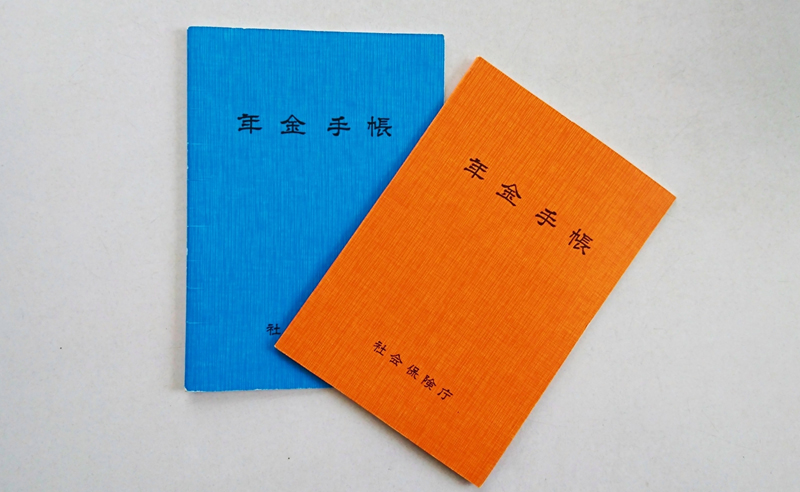



 葬儀・お葬式
葬儀・お葬式 参列マナー
参列マナー 葬儀後
葬儀後 法事・法要
法事・法要 終活
終活 葬儀前(事前相談)
葬儀前(事前相談)