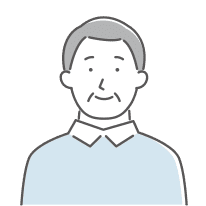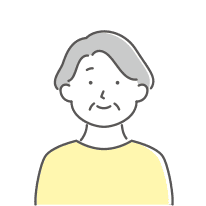仮通夜とは
「仮通夜」とは、亡くなったその日にごくごく身内(遺族・親族のみ)で行われる通夜のことを言います。
一般的に通夜と呼ばれるものは、正式には「本(ほん)通夜」と言い、お世話になった近隣の方々にもお知らせする形をとります。
通常は故人が亡くなったその日の夜に通夜、翌日に葬儀となりますが、僧侶や斎場の都合で葬儀が翌々日などになった場合、亡くなった当日の夜が仮通夜、二日目が弔問客を招く通常の通夜、三日目が葬儀となります。
そもそも本来の通夜とは?
仏陀が入滅した際、弟子たちが周りに集まって生前の仏陀の言葉を七日七晩話し合ったという逸話から、仏教で通夜を行う習慣が生まれました。
古くは一晩に限らず葬儀に至るまでの期間をずっと通夜と呼びました。
仏壇に常に線香を灯す文化は、仏陀が生まれた際、周囲に花が咲き乱れ良い香りが立ち込めたことに由来します。
仏教では故人は仏だと考えられるため、遺体のそばでも途切れることなく線香を灯すようになったのです。
また、遺体が損なわれたり、悪いものが憑いたりすることのないよう守るのも通夜の目的でした。
仮通夜・本通夜・半通夜の違い
本来の成り立ちから考えると、成仏に導く読経や説法は葬儀で行うもので、通夜は近親者が最後に故人と過ごす静かな時間であれば良いはずです。
しかし昨今では、通夜から僧侶が来て読経を行う、すなわち成仏を祈願する儀式になっています。
そういう意味では、仮通夜の方が本来の通夜の目的を保っており、喪服で窮屈になることもなく、また僧侶を接待する必要もなく、身内だけで故人の最後の顔を眺めしんみりとした時間を持てるひと時となります。
「本通夜」と「半通夜」という呼称に厳密な違いはありません。現代では遺族が本当に夜を徹して線香を灯し続ける「本来の通夜」を続ける地域は少なく、夜の2~3時間で終わらせるのが一般的です。
僧侶や弔問客がやってくる遅い時間を「本通夜」と呼んでも問題なく、実際には夜通しではないため「半通夜」と呼ぶ、といった現代の簡略化の流れで生まれた呼び名です。
地域による違い
仮通夜、本通夜、半通夜といくつかの通夜の形式がある中で、「仮」や「半」が付けられたのは伝統を簡素化したように思う引け目からでしょう。
しかし、亡くなった当日の通夜に僧侶と弔問客が集い翌日の葬儀で読経と会食がある、というのはあくまでも関東近郊の、近代の多数派の慣習例に過ぎません。
例えば秋田県では通夜自体を行なわない地域があります。
また、西日本や北海道では通夜と葬儀の区別がなく、通夜の読経に弔問客も参列してくれること自体が葬儀であるとの考えから、翌日の告別式を行わないところもあります。
東北の一部ではそもそも通夜は身内しか訪問せず、その他の弔問客は翌日の葬儀にだけ参列するのが習わしです。
地域ごとに意味づけと慣習があり、死者を思う気持ちがあれば、仮通夜、本通夜といった呼び方は厳格にこだわる必要はありません。
仮通夜の服装と香典について
仮通夜に参列する際は、遺族を慌ただしくさせないことに最も注意を払いましょう。
仮通夜は平服で構いません。「平服で」と言いながら準喪服が常識、といった葬儀とは違い、仮通夜は本当に身内だけが集まり静かに過ごす時なので、参列する者が喪服を着ていては遺族も落ち着きません。
光るアクセサリーや殺生を連想させる毛皮さえ避けていれば、落ち着いた色の普段着で構いません。
その方が呼んだ遺族もリラックスして過ごせるものです。
仮通夜には僧侶も来ず、身内とごく親しい親族だけが平服で集まり、通夜振る舞いなどの食事の用意もありません。
本来の通夜の目的に最も適った大切な時間の過ごし方なので、遺族が接待やしきたりなどを忘れて静かに故人の最後の時を過ごせるよう、参列者も普段着で訪問しましょう。
仮通夜では香典も不要です。香典は葬儀の時に出せば問題はありません。
逆に仮通夜に香典を出されても、遺族は香典返しの用意もなく、お食事の用意もしていないとなれば恐縮してしまいます。
前述したように、仮通夜では遺族に気を使わせないことが最も大切です。
これから弔問客の来る本通夜、葬儀と、遺族にとっては悲しみを味わう暇もない儀式の連続になります。
仮通夜はその前に、全てを忘れて遠慮のいらない近しい者達だけで過ごせるひと時なのです。
まとめ
葬儀の多くの面が簡略化される昨今において、仮通夜は本来の目的に適った静かな時間と言えます。
僧侶や斎場の都合で葬儀が伸びた際は、むしろ身内だけで仮通夜を過ごす一晩が持てることになり、良いことかもしれません。
故人との最後のひと時を大切に過ごされて下さいね。

























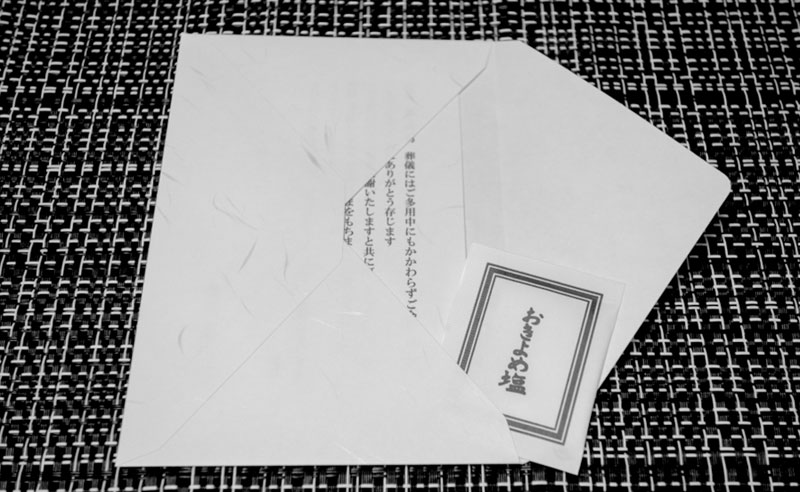


 葬儀・お葬式
葬儀・お葬式 参列マナー
参列マナー 葬儀後
葬儀後 法事・法要
法事・法要 終活
終活 葬儀前(事前相談)
葬儀前(事前相談)