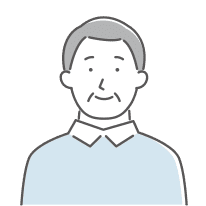お布施とは
お布施はお坊さんにお渡しするお礼の気持ちですが、お坊さんに納めていただくのではなく、お坊さんを通して最終的にはご本尊に捧げられます。
お寺側はお布施によってご本尊をお守りしている寺院を維持して法務(お寺の仕事全般)を行っています。
従って、お布施はご本尊を守るために使われるものなのです。
「お布施」と呼ばれるようになったのは「六波羅蜜(ろくはらみつ)」に由来します。
六波羅蜜とは、お坊さんの修行にある6つの徳目のことを指します。
この徳目の1つに分け与えるという意味の「布施」があり、布施はさらに「法施」「財施」「無畏施」に分けられます。
「法施(ほうせ)」はお坊さんの務めの1つで、人々を精神的に救うために正しい仏法を説くことを指します。
「財施(ざいせ)」は、人々が現金などの金銭や衣食を僧侶や生活に苦しんでいる人に分け与えるという、金品の施しのことを指します。
「無畏施(むいせ)」は、不安や恐れを持っている人が安心できるように支える、困った人に親切にする、といった人々の恐怖を取り除く行為のことです。
これらのうちお布施は「財施」にあたり、お坊さんが唱えてくれたお経である法施に対するお礼として差し上げるものです。
お坊さんと一般の人々が互いに助け合うことになるため、両者は良い関係を保てるとされています。
このように、謝礼として金品を施すことが布施の一部であることから、総じて「お布施」と言われるようになりました。
お布施の包み方
お布施の包み方には2通りの方法があります。
まず1つ目は和紙の一種である奉書紙(ほうしょがみ)で包む方法です。これは最も丁寧な包み方であると言われています。
まず初めに半紙でお札を包むか中袋にお札を入れます。次にお札の入った半紙や中包みを奉書紙(上包み)で包みます。
お布施は不祝儀にはあたらないため、上包みは弔事の折り方にする必要はなく、慶事の折り方と同様に上側の折返しに下側を被せます。
なお、奉書紙はつるつるした方が表面、ざらざらしている方が裏面です。
2つ目は白封筒に入れる方法です。
万が一奉書紙を用意できない場合はこちらの方法を用いると良いでしょう。
白封筒は、郵便番号欄が印刷されていない、二重になっていない、無地である、という3つの特徴を確認して選びます。
二重の封筒を使用しないのは、「不幸が重ならないように」という理由です。既に「御布施」とプリントされている市販の封筒を使う場合は、中袋に入れずそのままお札を入れて構いません。
お布施の表書きとお札の入れ方
お布施は不祝儀ではないため、薄墨ではなく普通の黒墨で表書きを書きます。
上部分に「御布施」と書き、下部分には「〇〇家」、もしくはフルネームか苗字を明記します。
裏面には住所・氏名・電話番号、そして入っているお金の金額を記載しましょう。本来は金額を書く必要はありませんが、お寺の経理・税務の記録を考慮すると記載しておいた方がより丁寧です。
なお、お布施に金額を記載する際は算用数字ではなく旧字体の漢数字を用います。
また、葬儀で用いる香典は「不幸に対してあらかじめ新札を準備している」という失礼を避けるために古いお札を使ったり新札に折り目を入れたりしますが、お布施に入れる紙幣は新札で構いません。
お布施はあらかじめ用意するもののため、新札を用いて問題ないのです。
またお札を入れる向きも香典とは逆向きで、お布施袋の表面に肖像画が上にくるように入れます。
お布施の相場
お布施の相場は一般的に3~5万円程度とされていますが、葬儀や四十九日法要、一周忌、それ以降の回忌など、タイミングによって金額が変わります。
初七日法要のお布施は戒名代も含まれるため、通夜と葬儀を合わせて30~40万円が一般的な相場です。
戒名の付け方によってはさらに値段が高くなる可能性もあります。四十九日法要の際は納骨をすることが多いため、納骨法要の謝礼を含めて6万円以上と言われています。
一周忌以降は他に追加する法要がないため、一般的な相場の3~5万円程度を包むと良いでしょう。またお車代は5,000円〜1万円程度、御膳料は5,000円〜2万円程度が相場です。
お車代や御膳料でお渡しするお金はキリの良い数字にするということに留意しましょう。
これらの金額はあくまでも一般的な相場のため、正確な金額を知りたい場合はお寺との打ち合わせの際に確認するようにしましょう。
またお墓の後ろに立てる卒塔婆(そとば)の代金が発生する場合もあるため、予算は多めに見積もることをお勧めします。
お布施を渡すタイミング
お布施を渡すタイミングは、お坊さんがお斎(おとき)と呼ばれる食事会に参加するかどうかによって異なります。
お斎に参加しない場合は、各法要後にお坊さんが帰る際にお渡します。お斎に参加する場合は、会食後にお坊さんが帰るタイミングでお渡します。
どちらの場合もお礼の挨拶を述べてからお渡しするのがマナーです。
また、身内以外の参列者がいる場合は、お布施を渡すところが人目に触れないように式場の外でお渡しした方が良いでしょう。
状況によってはお坊さんと最初の挨拶をする際にお渡しする場合もあるため、臨機応変な対応が求められます。
万が一タイミングを誤ってしまった場合は、お礼以外にも謝罪の言葉を一言添えましょう。
お布施を渡しそびれてしまうのだけは避けてください。
お布施を渡す際のマナー
お布施を渡す際はお盆に置いてお渡しします。
手でそのままお渡しするのは失礼にあたるため控えましょう。
お盆の大きさや形状は問いませんが、お布施専用の「切手盆」というものもあるため用意してもいいかもしれません。
なお、お布施の他にお車代や御膳料がある場合は、下から順に、御膳料、お車代、御布施と重ねるのがマナーです。
また、お布施などがお坊さんから見て正面になるように向きを揃えることにも注意します。渡す際は、お経を上げて下さったことに対する感謝の気持ちと、「お納めください」という一言を添えます。
長々と述べる必要はありませんが、冠婚葬祭の本やインターネットで添える言葉の例文を見つけることができるため、気になる方は事前に確認すると良いでしょう。
お布施の水引について
水引(みずひき)とは金封についている飾り紐のことを指します。
お布施は最終的にご本尊に対して渡すものであるため不祝儀には当たりません。
従って一般的には水引は必要ありませんが、地域やお寺によって異なる場合もあるため、気になる場合は確認しておくと良いでしょう。
お布施で水引が必要な場合は、多くは相銀や白黒の水引、特に関西では黄色と白の水引を用います。
水引をつける風習がなければ、水引をつけない方がむしろ丁寧な印象を与えることができます。
仏式以外のお布施について
日本における葬儀の大半が仏式ですが、場合によっては神式やキリスト教式の葬儀にも参列する機会があるかもしれません。
いずれの場合も仏式のお布施にあたるものがあり、表書きの名称は違っても多くの共通点が見られます。
以下ではそれぞれの儀式の概要やお布施にあたるものについて解説します。
神式のお布施について
神式とは、八百万の神を祀る神道(しんとう)という宗教に則った祭典や儀式のことを言います。
葬儀の翌日に翌日祭、亡くなった日から10日ごとに十日祭、二十日祭、三十日祭、四十日祭と続き、五十日祭をもって忌明けとなります。
仏式の葬儀や法要にあたるものを「霊祭」や「祖霊祭」と呼び、「祭祀いただいたお礼に代えて」という意味で、仏式のお布施にあたる「祭祀料」をお渡しします。
神式のお布施の表書きは「御祭祀料」です。金額の相場は事前に神社に相談すると良いでしょう。
また、この他にも状況に応じてお車代や御膳料をお渡しするのは仏式と同じです。
キリスト教式のお布施について
キリスト教には大きく分けてカトリックとプロテスタントという2つの宗派があり、それぞれ3日目、7日目、1ヶ月目、1年後にミサを行います。
キリスト教では死は永遠の始まりであり不幸なことではないと考えられるため、お悔やみの言葉は伝えず、また聖歌や讃美歌斉唱がある場合はできるだけ参加するのがマナーになります。
カトリックでは神父に、プロテスタントでは牧師に教会にて説教を説いてもらいます。カトリックでは、ミサ終了後に神父の説教に対する感謝の気持ちとして「謝礼」をお渡しします。
プロテスタントでは教会への寄付の意味で牧師に「記念献金」をお渡しします。
この他、オルガン奏者にも別途金封をお渡しし、さらに式に携わってくれた信者の方々にお菓子などを配る場合もあります。
「謝礼」や「記念献金」の明確な金額は、仏式や神式同様に事前に教会に確認するのが無難です。
まとめ
この記事ではお布施の相場やマナーについて解説しました。
お布施と一言で言っても、宗教によって意味が異なること、その時々の法要によって金額が変わること、渡し方にも作法があることなど、押さえておきたいポイントをお分かりいただけたかと思います。
何より故人のために、お坊さんやお寺へ感謝の気持を持ちつつマナーを守ってお布施を用意したいものですね。

























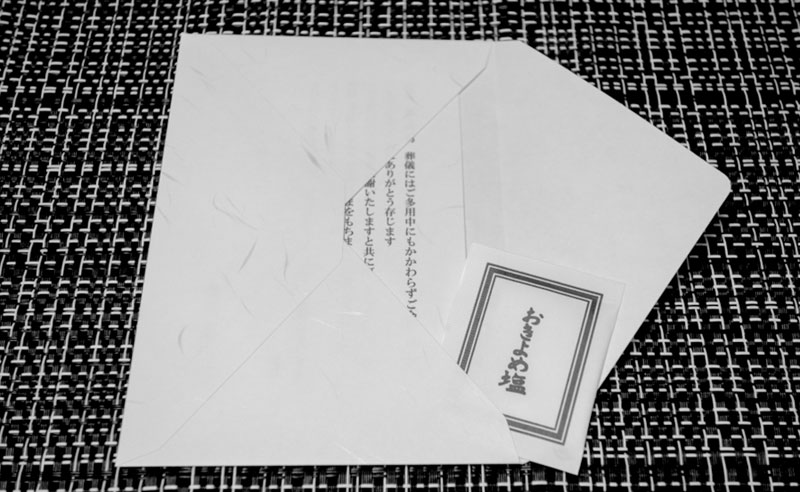


 葬儀・お葬式
葬儀・お葬式 参列マナー
参列マナー 葬儀後
葬儀後 法事・法要
法事・法要 終活
終活 葬儀前(事前相談)
葬儀前(事前相談)