葬儀保険とは
葬儀を執り行うにはそれなりの資金が必要です。事前に準備していないといきなり支払うのは難しく、たとえ払えたとしても家計にも影響するでしょう。このような負担の軽減を目的として誕生したのが「葬儀保険」です。保険と名の付くとおり、事前に保険料を納めていざという時の出費に備えることができます。
一般的に保険には色々な種類がありますが、葬儀保険は「少額短期保険」に該当します。
別名「ミニ保険」とも呼ばれ、目的が明確な保険なので、保証の内容も分かりやすくなっています。
特徴としては、保険の金額が少額であるということ、そして保険の期間も短期であるということが挙げられます。
具体的には、保険期間は1年、保険金額は300万円以下と定められています。
葬儀など急な需要に対応できる新しいタイプの保険です。
葬儀にかかる費用
ではそもそも葬儀に際してはどのような費用が発生するのでしょうか。
葬儀と聞くとかなりお金がかかるというイメージをお持ちの方も多いでしょう。
葬儀費用は規模や地域によってまちまちですが、全国の平均的な相場は約200万円と言われています。
費用は大きく分けて「葬儀本体の費用」「飲食接待の費用」「寺院へのお布施」の3つとなります。
それぞれの費用について、以下で詳しく見ていきましょう。
葬儀費用一式
お葬式の儀式そのものに必要な費用です。
セレモニーホールなどの葬儀会場の使用料、火葬場の利用料、葬儀に関わるスタッフの人件費、祭壇や棺にかかる費用など、お通夜・葬儀・告別式を執り行うのに必要な基本的な費用が含まれます。
葬儀費用一式の平均費用は約122万円です。葬儀全体の費用に占める割が最も大きいのがこの項目です。
飲食接待費
飲食接待費は飲食にかかる費用とお香典の返礼品などにかかる費用を指します。
飲食にかかる費用とは、具体的には、お通夜の後に参列者をもてなす「通夜振る舞い」と、告別式の後に用意する「精進落とし」が含まれます。
飲食接待費の平均は約34万円ですが、弔問に訪れた参列者の人数によって変動するだけでなく、料理のグレードでも金額は変わります。
お布施
葬儀を執り行うには、読経や戒名のお礼として僧侶に渡すお布施も準備する必要があります。
仏教においてお布施は「布施行」という修行の一つと考えられており、基本的にははっきりとした金額は提示されません。
菩提寺とのお付き合いの度合いによっても金額は変化しますが、相場は4~5万円です。
葬儀保険の種類
このように、葬儀を執り行うにはまとまったお金が必要です。
一度に準備するのは難しい場合もあるでしょう。
そこで活用を検討したいのが葬儀保険です。
各保険会社が様々な葬儀保険を提供していますが、自分に合った葬儀保険はどのように選べば良いのでしょうか。
以下では保険料の支払額に応じた2つの種類をご紹介します。
保険料一定タイプ
毎月支払う保険料が変動しないタイプです。
加入するハードルは相対的に低くなりますが、年齢が上がるにつれて受け取れる保険金額が減額されていきます。
資金にある程度余力がある方は後述する定額タイプがおすすめですが、徐々に保険料が上がることに不安を感じる方はこちらのタイプが良いでしょう。
保険金定額タイプ
受け取れる保険金が変わらないタイプです。
契約時に設定した金額が仮に100万円なら、どんなに年齢が上がっても遺族は100万円を受け取ることができます。
ただし、年齢に応じて毎月支払う保険料は高くなるため注意が必要です。
高齢になっても支払える方は、資金面での葬儀計画が立てやすくなりおすすめです。
葬儀保険が人気の理由
葬儀にかかる費用と葬儀保険の概要についてご紹介してきました。
「死」は全ての人にいつかは訪れるものですが、高齢になるにつれて不安が大きくなったり、若くても大切な家族になるべく迷惑を掛けないよう早くから準備をしたいと思ったりするでしょう。
そのような不安や思いに答えるものとして誕生した葬儀保険が昨今注目を集め、多くの人に実際に活用されていることも頷けます。
以下ではその人気の理由について、改めて整理してご紹介します。
医師の診断が不要の場合が多い
保険というと、加入するにあたって様々な条件があるのが一般的です。
例えば年齢や健康状態などが典型的ですが、場合によっては健康状態を保証するために医師の診断書が必要とされることもあります。
中にはこれらの条件をクリアできず保険の加入を諦めたことがある方もいるかと思います。
保険加入における特に大きなハードルとなる医師の診断書は、葬儀保険においては提出が不要とされている場合が多くあります。
自身の健康状態などの自己申告義務も不要としている葬儀保険会社も増えており、持病がある人でも現状の健康状態に問題がなければ加入することができます。
高齢でも契約できる
年齢も保険加入のハードルになることがありますが、葬儀保険の場合は他の保険に比べて年齢の条件が緩い場合があります。
多くの葬儀保険が85歳頃まで加入可能としており、保障期間も99歳~100歳まで約束されている商品が数多く存在します。
葬儀を現実的に考えるようになる高齢者にとって、高齢になってからも加入することができるのはとても大きなメリットでしょう。
保険金の支払が早い
一般的な保険の場合、保険金請求の書類送付から実際の保険金振込みまでに、概ね5営業日~1週間ほどかかると言われており、急を要していてもある程度のタイムラグは見越しておかなければなりません。
また、故人の預金口座などは一時的に凍結される可能性もあるので、必要な時にお金が使えないというリスクもあります。
一方、葬儀保険は葬儀費用を補うという明確な理由のある商品であるため、多くの商品が書類到着後の翌日には保険金が支払われます。
葬儀に際してすぐにお金が必要でも困る心配がなく、また葬儀保険は受取人を事前に指定することも可能なので、よく聞くお金のトラブルも回避しやすいでしょう。
支払う保険料が割安
前述したとおり、葬儀保険は「少額短期保険」に該当します。
年齢によっても金額は変動しますが、50~69歳の場合は月額1,000円前後の商品が数多くあり、中には月々の支払いが定額で数百円程度のものもあります
総じてとてもリーズナブルで、多くの人が手を付けやすい商品です。
言うまでもありませんが、保証を厚くしたい場合はその分保険料も上がるので、自分の経済状況と将来的な目標とを考慮して最適な保険商品を選択しましょう。
葬儀保険の注意点
いくら月額保険料が安価だとしても、葬儀保険は決して安い買い物ではありません。
保険に加入した後に後悔しないように、以下のポイントに留意して葬儀保険を検討しましょう。
虚偽の告知を行わない
葬儀保険に限りませんが、保険加入をする際に最も気をつけなければいけないのが「告知義務違反」です。
保険加入には医師の診断書や告知書の提出が必要ですが、そこに事実と異なることを書いたり報告すべき重要な事柄を隠したりすると告知義務違反に当たり保険の契約解除や保険金の不払いに繋がります。
どんなに保険に加入したくても、小さな嘘を付くことで大事な保険金が受け取れなくなってしまえば元も子もありません。
正直な告知を徹底しましょう。
保険の責任開始期を認識する
契約を結んだからといって、すぐに保険の保障期間が開始するとは限りません。
保険には責任開始期というものが設定されており、それまでの一定期間は何か身に起こったとしても保険は適用されません。
申込日と保障開始日である責任開始期を混同しないように注意しましょう。
責任開始期は多くの商品が契約日の翌々月1日からとしていますが、実際の契約にあたっては保険の契約内容をよく確認する必要があります。
保険契約者保護機構の保証対象外であることを知っておく
「保険契約者保護機構」とは、保険会社の経営が上手くいかずに破綻した場合に保険契約者を保護するための機関です。
保険契約者保護機構は保険業法で決められているものですが、葬儀保険はこの保証の対象外になります。
葬儀保険を扱う保険会社は少額短期保険業者にあたるため、他の大手生命保険会社のような保険契約者保護機構による保護はないのです。
そのため、葬儀保険を選ぶ際は、保険内容の吟味もさることながら、葬儀保険会社が信頼に足る会社かもよくリサーチしましょう。
例えば、会社の評判や財務状況、信頼性はよく確認すべきです。
大切なお金を任せられる会社を選びましょう。
まとめ
本稿では葬儀保険について解説しました。
保障内容をよく確認し自分に合った保険を選択できれば、葬儀に向けて賢くお金を備えられます。
もしもの時の準備を行っておけば、日々の生活に安心感が生まれ、いざという時は大切な家族を助けることができます。
葬儀保険を上手に活用して、終活で一歩リードしたいものですね。

















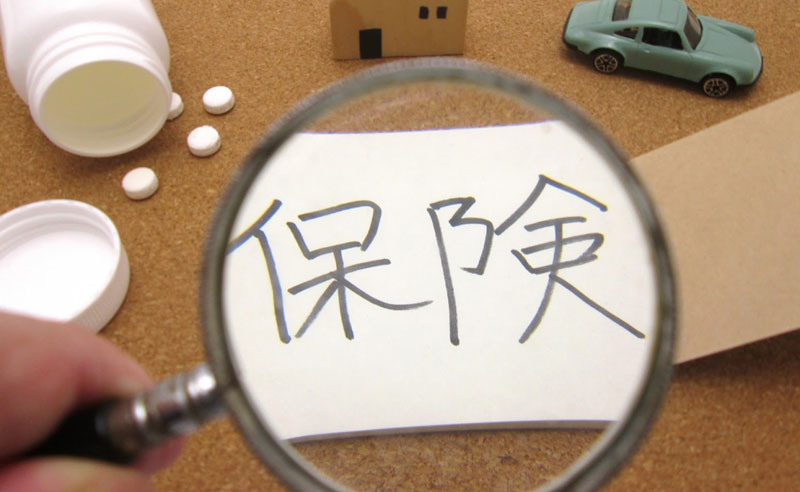
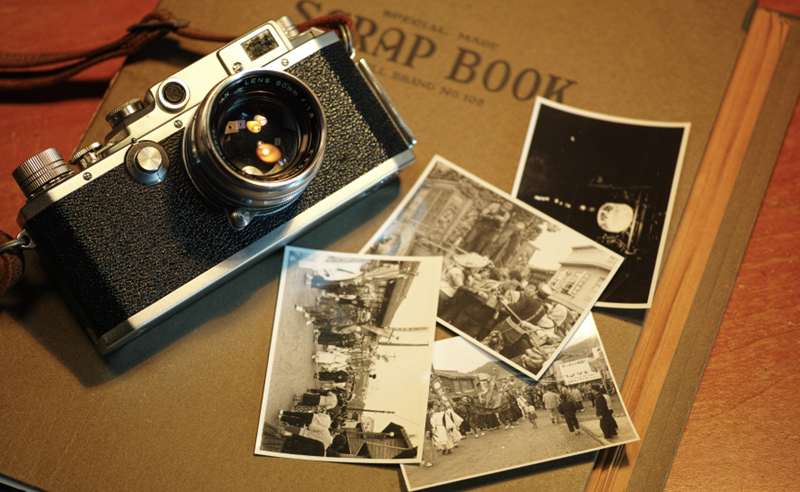





 葬儀・お葬式
葬儀・お葬式 参列マナー
参列マナー 葬儀後
葬儀後 法事・法要
法事・法要 終活
終活 葬儀前(事前相談)
葬儀前(事前相談)
























