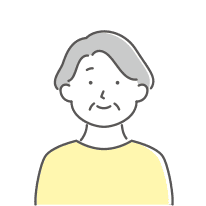葬式の流れと時間帯
「葬式」とは、通夜の翌日に行われる「葬儀」の別の言い方です。
ただし、初日の通夜から次の日の告別式の後の火葬までの一連の流れを指して、便宜的に「葬式」、もしくは「葬儀」と呼ぶことがあります。
ここでは、通夜、および葬儀・告別式について、それぞれの式の流れと行われる時間帯をご紹介します。
通夜について
故人を偲ぶために葬儀の前日に行う儀式を「通夜」と呼びます。
通夜は、古代日本において行われてきた「殯(もがり)」という風習に由来するもので、故人と近い関係の人が集い、線香やろうそくの火を絶やさぬようにしながら、故人との時間を夜通し過ごすというのが本来の形のものでした。
これは、野生の動物などから故人をお守りする意味合いも兼ねられており、「夜伽(よとぎ)」、または「棺守り」とよばれるものでした。
現代においては、故人の友人や仕事仲間等の一般の参列者が来ることのできる時間に行われるようになり、晩御飯を振る舞ったあとに解散する「半通夜」が一般的になっています。
通夜の流れ
ここでは通夜の流れについてご紹介していきます。
通夜は、一般的に故人の死の翌日に行われます。
1.着席~僧侶の入場
着席をする際の席順は、喪主を筆頭とし、故人との血縁の近い順に家族単位で席順を決めていきます。
通常の場合、祭壇に向かって右側に遺族、左側に故人の友人や職場の上司、同僚などの人が着席します。
通夜の開始時刻になり次第、葬儀社の担当者が僧侶をお呼びして、通夜がはじまります。
2.僧侶による読経と参列者の焼香
通夜が始まると、僧侶が経典を読み上げます(読経)。
その後、僧侶あるいは担当者の指示にしたがって焼香が始まります。
順番を守って、堂々と振る舞いましょう。
3.僧侶の退場、喪主のあいさつと通夜振る舞い
僧侶の退場の際、遺族は黙礼して見送ります。
その後、喪主は参列者に向けて、参列して下さったことへの感謝と、故人の生前、及び病気等で療養している際の厚情に対する感謝の気持ちを伝えるあいさつを行います。
その後、通夜振る舞いの席へと参列者を招きます。
通夜振る舞いは、喪主が会葬者に感謝の意を伝える接待のことを呼びます。
参列者は故人を偲びながら、用意された料理に箸をつけます。頃合いを見て喪主が閉めのあいさつをし、散会となります。
通夜を行う時間帯
通夜が行われる時間帯は、一般的に18時から21時くらいまでとする場合が多いです。
開式は遅くとも19時にはなされ、通夜の受付は開式の1時間前、遅くとも30分ほど前には始めます。
仏式の場合、僧侶による読経と、遺族と参列者による焼香が行われます。
その後、飲食を振る舞うことで遺族が駆けつけて下さった参列者への感謝の気持ちを表す、「通夜振る舞い」を、1時間から2時間ほどの時間をかけて行います。
散会は、地域のしきたりや、参列者の数などによる変動はありますが、遅くても21時頃になることが多いです。
葬儀・告別式について
葬儀・告別式の両式は同じものだと認識されがちですが、違いがあります。
葬儀は、故人の成仏を願い、弔うための宗教的な儀式ですが、告別式は、遺族と参列者が故人にお別れをするための儀式です。
本来、二つの式は、別々に行われていましたが、近年では一緒に行われることが多くなっています。
厳密に言えば、儀式が始まってから遺族や親族の焼香が終わるまでが「葬儀」であり、参列者が焼香を始めてから閉式までを「告別式」と呼称します。
宗派によってやり方は異なりますが、僧侶が入場し、開式の辞が述べられるのをもって式の開始となります。
葬儀・告別式の流れ
ここでは二つの式の流れをより詳細にご紹介していきます。
1.着席~開式
遺族および参列者は開始時刻より前に着席します。
祭壇に向かって右側に遺族や親族、左側に故人の友人、職場の人などが着席します。
開式の時間になると、僧侶が入場します。
遺族と参列者は合掌し、黙礼をする形で僧侶を迎え、開式の辞が述べられた後に葬儀が始まります。
2.読経、弔辞と弔電~焼香
通夜と同様に、経典の読誦である読経が行われます。
宗派によって異なりますが、読経はおおむね40分~60分程度行われます。
そのなかで、故人には戒名が授けられ、浄土へと導かれます。これを「引導」と呼びます。
その後に故人の友人や、上司などの適任者によって弔辞が述べられます。
弔電は、葬儀社の担当の方が数通を読み上げ、残りは名前のみを読み上げます。
その後、もう一度僧侶がお経を読みます。
焼香はこの時に行います。順番は、喪主、遺族、親族、参列者の順です。
3.閉式の辞
焼香が終わった後に僧侶が退場するので、入場の際と同じく合掌と黙礼で見送ります。
その後に閉式の辞が述べられ、閉式となります。
葬儀・告別式を行う時間帯
れらの式を行う時間は、午前10時から12時の間の2時間ほどです。
葬儀社によっては、余裕を持ってより長い時間をかけて執り行うこともあります。
通夜同様、式が始まる1時間から30分前にまず受付を行います。
開始される時刻は通常、その後に火葬を行う地域は火葬場の予約時間から逆算して決められます。
一方で、前火葬といって、事前に火葬を行う地域では、葬儀を通夜の翌朝に、喪主をはじめとする遺族による出棺、火葬の後に行います。
いずれにしても、葬儀式場も夕方には別の葬家の通夜が始まることから、午後に行う場合も13時頃、遅くとも14時には開始されることが多いです。
葬儀の日程を決めるポイント
日本人の宗教観が変わってきたことや、核家族が増えたことで近所との付き合いが減ったことなどの要因から、現代では火葬のみを行う「直葬(ちょくそう)」という形も選ばれるようになってきており、
その場合は葬儀社と親族への連絡、火葬場の予約程度で行うことができますが、通常の葬儀の場合、そうはいきません。
日程を決めるためにあらゆる方面の都合や状況の調整を行わなくてはならないためです。
ここでは、葬儀の日程を決めるポイントについてご紹介していきます。
斎場や火葬場の空き状況を確認する
まず、斎場や火葬場の空き状況を確認しておくことは重要なことです。
家族葬であれば、規模の大きい式場でなくて良いですし、反対に参列者の人数が多い場合は、それ相応の規模と設備を擁した式場である必要があります。
もちろん、喪主や遺族の希望にも沿った式場を選ぶ必要もありますから、葬儀の際の斎場は、どこでもいいというものではないのです。
また、火葬場の中でも都心にある火葬場は、常に稼働率が高く、11時から13時までの火葬枠からあっという間に埋まっていってしまいます。
朝の早い時間帯では遺族の方への負担が大きく、昼過ぎの遅い時間帯では、当日に通夜を控えている次の葬家に迷惑がかかってしまう、という2つの理由から、「何時までに出棺しなければならない」と式場側が決めているところも存在するほどです。
こうした状況から、葬儀の日にち自体を延ばさなくてはならなくなる事例もあるのです。
宗教者の都合に配慮する
葬儀を先導する役割を担うのは、宗教者(仏式であればお寺のお坊さん)であることを忘れてはなりません。そのため、こちら主導でどんどん話を進めてしまわずに、宗教者の都合にも配慮するようにしましょう。お互いに良い関係で式を執り行うことが成功への秘訣です。
寺院が菩提寺の場合は、葬儀に先立って必ず連絡を入れ、菩提寺の都合を伺い、それを尊重するようにしましょう。
しかし、寺院との付き合いがなく、葬儀社から紹介してもらう場合は、遺族の希望する日程で来て下さる僧侶のいる寺院を紹介してもらえます。
参列する親族のスケジュールを確認する
また、葬儀に参列する親族の方のスケジュールも確認した上で、どのような日程を希望するかの相談を葬儀社と一緒に行います。
葬儀に参列するために予定を空けてくださっていたり、もともと予定が空いていたりすればすんなりと日程が決まりやすいのですが、親族が仕事で多忙であったり、どうしても外せない予定がある方がいる場合は、それを尊重して葬儀日程を組むと良いでしょう。
しきたりを確認する
地域の風習やしきたりがある場合、その点にも考慮することが望ましいといえます。
自分が気にしない、という場合であっても、特に年配の方には気にする方が多いことにも配慮しましょう。
葬儀を行う際は、縁起の悪い出来事に友人を引き寄せてしまうという印象があるという理由で「友引」の日を避ける風潮があります。
火葬場も友引の日は休業しているところが多いです。
また、地域によっては亡くなった当日の夜に通夜を行う地域も存在します。
葬儀を行う前に、カレンダーや住んでいる地域ならではの風習や、しきたりの有無について確認をしておくことも必要になるでしょう。
まとめ
この記事では、通夜と葬儀・告別式の流れと時間帯について、お葬式の日程を決めるにあたって考慮が必要なポイントについてご紹介しました。
いずれも故人をしのび、その死を悼み、冥福を祈るための重要な儀式です。
それゆえ日程の決定などの準備はしっかりと行わなくてはなりません。
ポイントを押さえた日程調整を行い、速やかな開式を心がけましょう。
この記事が、葬儀の日程決めを円滑に行っていく助けとなりましたら幸いです。

























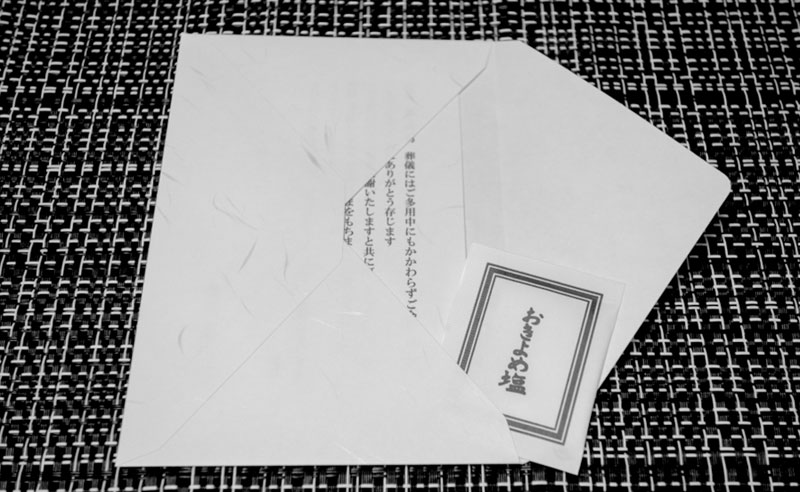


 葬儀・お葬式
葬儀・お葬式 参列マナー
参列マナー 葬儀後
葬儀後 法事・法要
法事・法要 終活
終活 葬儀前(事前相談)
葬儀前(事前相談)