代表的な祭壇は3つ
葬儀といえば、遺影のまわりにお花があしらわれた祭壇をイメージすると思います。
祭壇とは、神や仏に供物を捧げる壇のことです。
本来はシンプルな白木の台でしたが、近年では様々なお花を敷き詰めた花祭壇が主流となりつつあります。
また、宗教によっても祭壇は様々で、お花を飾らない祭壇もあります。
ここでは、代表的な3つの祭壇、白木祭壇と花祭壇、神式祭壇についてご紹介します。
白木祭壇とは
昔は棺桶も横長ではなく、樽のような形状の中に座った形でご遺体を収めました。
それを白木で作った輿(こし)に乗せ、村の者が担いで墓地まで野辺送りをしたのです。
樽型だった「座棺」が、横になったまま遺体を収められる「寝棺」になると、野辺送りも豪華仕様のリヤカーで行いました。
それがいつしかトラックの荷台になり、霊柩車になり、現代に至ります。
白木祭壇は以前の輿を再現したもので、白木祭壇の最上部にある屋根は輿の屋根部分を表しています。
仏教の葬儀では白木祭壇の下段に遺影や供物を置き、祭壇の前に経机(きょうづくえ)を置き、そこで僧侶が読経を行います。
葬儀社には備品として備わっており、遺族の要望に応じて左右に袖を追加するなどしてカスタマイズします。
厳格で荘厳な雰囲気があるのは、昔ながらの輿を再現した白木祭壇ならではです。
花祭壇とは
何段にも創られた白木の祭壇の代わりに花で埋め尽くした祭壇を花祭壇と呼び、昨今人気が出てきています。
生花の祭壇よりも価格を抑えられる「造花」の祭壇も、近年では増えてきました。
葬儀の花と言えば昔は菊や曼殊沙華が定番でしたが、花祭壇では洋花や明るい色の花なども多用されるようになっています。
葬儀はタイトなスケジュールで用意をする場合もあるので、全ての花を好みで指定するのは困難ですが、葬儀社のパッケージの中に故人の好きだった花を1種類混ぜるなどして個性を出せる場合もあります。
花祭壇が広まった背景には、白木祭壇の値段の高さもあります。
神式祭壇とは
神道の葬儀で使用される祭壇のことです。神葬祭の祭壇には、三種の神器や幣帛など、様々な物を供えます。
また、神様へ献上する食事も用意します。供えられるのは、米・酒・海の幸・山の幸・塩・水など。
造花祭壇に使われる花
造花祭壇は生花の代わりに造花を使いますが、昨今の造花の技術向上は素晴らしく、生花と見間違えるレベルです。
「造花」という単語のイメージを避けるため、「アートフラワー祭壇」と呼ぶこともあります。
ただし、造花だと言うことを名言せずに「花祭壇」と謳っている業者もあるため、造花か生花かはきちんと把握した上で選択したいものです。
以下では造花祭壇で使われる花についてご紹介します。
シルクフラワー
シルクフラワーは「造花」の新語です。昔の「造花」は、茎は明らかなプラスチック製、葉は生気がなくペラペラ、そして花は自然界よりも派手で濃すぎる色のものが付けられていました。
これに対し、シルクフラワーは昔の造花のイメージからは桁違いに高品質であることを区別するために生まれた呼称です。
非常に繊細で本物と見紛うクオリティがあり、生花の代わりとして一流ホテルなどでも多用されています。
本物の華道家の方がシルクフラワーを使ったアート作品の制作に転身されることもある程です。
別名「アーティフィシャル(人工)フラワー」とも呼ばれ、昨今人気が高まっています。
プリザーブドフラワー
プリザーブドフラワーは、生花の中に薬品を注入し、色と水分を何年も保てるように加工したものです。
枯れない生花なので、乱暴に扱えば花びらが落ちてしまうなど繊細さは生花と同じです。
プリザーブドフラワーであれば生花であることに違いはないので、生花祭壇よりも低料金で本物の花祭壇をつくることができます。
生花祭壇
生の花を使う生花祭壇では、どのような花が用いられるのでしょう。
昔ながらの菊、百合から、カーネーションと胡蝶蘭まで、現代の代表的な花の種類を説明します。
菊
キク科キク属の多年草植物です。
皇族の紋章でもあり、日本の象徴でもあります。丈夫で長持ちすることから、ヨーロッパでも墓参りの花として定着しています。
中国から伝わり日本の宮中でも行われていた重陽の節句では、9月9日の前日夜に菊の花の上に綿をかぶせ、翌朝夜露に濡れた綿で顔を撫でると美肌になると言われました。
邪気を払う花としての菊は日本でも仏花として定番となりました。
白菊は白、黄色菊は黄色とはっきりした単色の花のため、花祭壇においては色のグラデーションを出しやすく、ダイナミックな花のウェーブが作れます。
ユリ
ユリ科ユリ属の多年草です。
世界中に分布しており、大きく優雅な花は高貴で厳かな場に良く似合います。
花祭壇には菊、カーネーションなど日持ちがし扱いやすい花が用いられることが多い中、百合は日持ちせず花弁もすぐに色褪せます。
しかし非常に香り高いため、花祭壇に百合を多用すると会場に良い香りが立ち込めます。
その場を豪華な雰囲気にし、1日だけで撤去するには最も適した花です。
なお、百合の花粉は衣服に付くと色が取れないため、必ず花粉を取ってから活けます。
墓石などに落ちても色が落ちないため、お墓参りの際も花粉を取ることをお勧めします。
カーネーション
ナデシコ科ナデシコ族の多年草です。
南欧、及び西アジアが原産ですが、母の日に贈る花として日本でも急激に普及しました。
持ちやすい茎、丈夫な花弁から、欧米でも葬儀での献花としてよく用いられます。
日持ちがし、花弁が茎から折れることもないため、大量の花と共に花祭壇に活ける際、非常に扱いやすい花であると言えます。
菊よりも明るめの赤のため、色のグラデーションを出す際にも便利です。
胡蝶蘭
コチョウラン属の着生植物(土に根を下ろさず、他の木などに着生する種族)です。
東南アジア原産で、何個も連なった白い花は高貴で大変長く日持ちするため、贈答用の花として人気です。
花祭壇においても単調な花と茎だけの連なりに変化を起こす見た目となるため、遺影周りに集中的に用いられます。
葬儀で用いられる花の名称
花祭壇の他にも、葬儀には沢山の花が飾られます。
枕花、供花、献花から花輪まで、意味や理由と、贈り方の仔細を見てみましょう。
枕花
枕花(まくらばな)とは、故人と特に親しかった者や近親者が、訃報の知らせを聞いてすぐに贈る花のことです。
遺体が自宅に戻った際、枕元に飾って下さいという気持ちを込めて、文字通り枕元に収まる程度の小さな籠花を贈るのが定番です。
これは遺族に対して「悲しみを分かち合います」という気遣いでもあり、白や青などの控え目な色の花を選んで贈ります。
白菊に白百合、のような白の掛け合わせも品があって美しいでしょう。
値段の相場は5,000円~30,000円で、大型の花輪などのように大々的に名前を記すこともなく、送り主の名を書いた小さなカードを添えて送ります。
花輪などは葬儀会社に片付けられてしまいますが、葬儀が終わった後でも遺族が自宅に返って我に返るとき、枕花はずっとそこにあるため、特に親しかった方からの気持ちとして遺族を支えてくれることもあるでしょう。
供花
供花(きょうか)は、「香典の他に供物としての花を供する」意で、葬儀の場に贈る花全般を指します。
仏陀が亡くなった際、天から宝花が降ってきて供養したという故事を元に、人が亡くなった際は、誰でも花を贈ることができます。
自宅や葬儀場に届いた花は、斎場の入口や祭壇の周りに飾られます。
門の左右や会場の左右に対で置けることから、供花は二つペアで贈るものという慣習が以前はありましたが、現代では一つでも贈ることが増えています。
贈りたい場合は葬儀案内状の斉場に連絡し、供花の依頼をします。
個別に送っても良いか、統一感を出すために業者さん指定で揃えるべきかなどを確認してから贈りましょう。
花環
輪の形に飾りつけた花、もしくは造花が花環です。
葬儀だけでなく祝い事にも贈られます。
葬儀の花輪は白と黒をベースにした色組で、花環の下の足台の部分に送り主の名前が書かれます。
花環は少し古い習慣になりつつあり、田舎では慣習として根強くある地域もありますが、都市部では景観への苦情から斉場の周りでも花輪を屋外に置けない地域が増えており、減少の傾向にあります。
代わりに屋内の祭壇に飾れる供花が贈られることが増えています。
花環にこそ地方の特色があるので、贈る際は必ず斉場に問い合わせてから発注しましょう。
献花
献花(けんか)とは葬儀の場で霊前に花を供えることを指します。
主にキリスト教の葬儀で行われる儀式で、仏式の焼香の代わりに、参列者一人一人が手に持った花を棺に供えていきます。
欧米でも、茎が長くて持ちやすく、花のクビが丈夫な菊やカーネーションが用いられることが一般的です。
花は遺族によって人数分用意されているため、受け取って棺に近づいた後、遺族と遺影にそれぞれ一例してから、棺の上に花を供えます。
花の向きは右向きの場合と会場側を向いていることがあるので、前の方に倣いましょう。
キリスト教以外にも、無宗教葬や家族葬などでも、献花の儀式を取り入れることが増えています。
まとめ
昔は菊以外の選択肢が少なかった葬儀の花も、時代と共に様々な種類が増えました。
白木祭壇でも花祭壇でも、故人への思いを込めれば双方良い葬儀になるでしょう。
故人のための最後の儀式として、納得した知識を持って花も選びたいものです。



















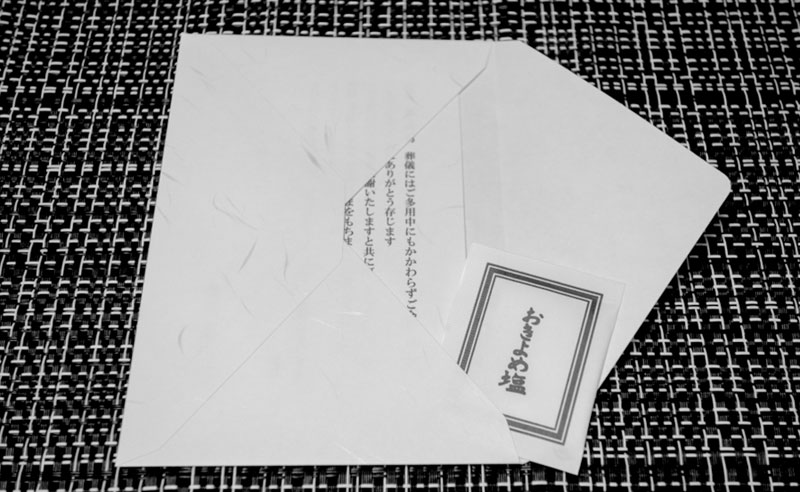


 葬儀・お葬式
葬儀・お葬式 参列マナー
参列マナー 葬儀後
葬儀後 法事・法要
法事・法要 終活
終活 葬儀前(事前相談)
葬儀前(事前相談)
























