火葬とは
火葬は遺体を埋葬する方法のひとつであり、遺体を高温焼却して、お骨や灰に変えることです。
日本では専用の火葬場が全国に設けられており、告別式を済ませた後に実施される場合が大半です。
火葬場へ参列するのは遺族や親族、故人と縁が深い友人の方など、少人数であることが一般的です。
日本で火葬が主流になった背景
仏教式での葬儀が多い日本では、自然と火葬が実施されることが多いです。
日本で火葬が初めて実施されたのは紀元700年とされており、仏教が国内に広まっていくと同時に火葬が主な葬儀方法となったようです。
世界的には土葬が主流
仏教では火葬が主流ですが、キリスト教やイスラム教では土葬が主流とされています。
世界的に見ると信仰者が最も多いキリスト教と、2番目に多いイスラム教が両方とも火葬を禁じていることから、世界全体でみると土葬が最も広まっている埋葬法であるといえます。
しかし、近年ではプロテスタント系を中心としてキリスト教圏でも火葬が取り入れられています。
これはカトリック系との宗教間の違いが理由にありますが、物理的に土葬する敷地が不足してきたというのが主な理由とされます。
とは言え、カトリック系のキリスト教圏およびイスラム教圏では今でも土葬が主流であることから、葬儀方法は各地域によって異なっているのが現状です。
日本も昔は土葬だった
日本では火葬が埋葬方法の大半を占める印象があると思われますが、20世紀初期あたりまでは土葬が主な方法だったようです。
明治時代に火葬炉が造られる以前は屋外で執り行うことが常識となっていたので、衛生的・コスト的にも火葬を敬遠する人が多かったとされます。
明治時代になって土葬に用いる敷地が不足してきたことから、明治時代初期から現代と同じような設備や法令が整えられています。
しかし国内で火葬率が5割を上回ったのは1940年ごろであり、殆ど100%となったのは2015年になってからです。
現代の日本の火葬率は99.99%
現代では、日本国内での葬儀の殆ど全ては火葬で実施されています。
世界的に見ても実施例が多く、遺骨を残す風習が広まっている事から、遺骨を破損させずに残す技術が特に発展しているようです。
加えて、火葬することで埋葬スペースを節約できる事と、埋葬した遺体が感染症を媒介するリスクも殆ど防げるなど、合理的な点が多いことから火葬を取り入れる国も増えつつあるようです。
火葬許可されるまでの手順
日本国内で火葬を実施するには「火葬許可証」が必須です。
火葬場まで許可証を持参することで、実施手続きに移れるようになります。
身内が亡くなった際は、故人の死亡届を市役所まで提出する必要があります。
届出を行うと同時に、火葬許可の申請も併せて実施することで火葬許可証を発行してもらう事ができます。
申請には「死体火葬許可申請書」を当日に記入・提出する必要がありますが、書類に不備がなければ申請した当日に火葬許可証を発行してもらえます。
仮に書類に不備があった場合でも、届け出を行う方の印鑑(認印可)があれば対応可能です。
なお、家族を持たない方が亡くなられた場合は、親族や同居者、地主や大家などが火葬許可の申請を実施することが出来ます。
火葬から骨上げまでの流れ
火葬当日は、会場へ向かうところから最後の骨上げまで多くのマナーが存在します。
火葬後に埋葬を実施するときに必要な書類も火葬当日に受け取るので、基本的な流れやマナーは把握しておきましょう。
火葬場到着
告別式が終わって出棺した後、参列する人は火葬場へ移動します。
道中は霊柩車を先頭にして、火葬場までを移動します。
到着したら、火葬場のスタッフに「死体火葬許可証」を提示します。
帰りまではスタッフが預かり、火葬が終了したら「火葬済証明印」が押された許可証を受け取ります。
この許可証は埋葬を実施する際に必要なので、必ず手元に保管しておきましょう。
なお、分骨することを予定しているときはここで火葬場スタッフへ分骨を行う旨を伝えましょう。
火葬
火葬炉の前まで到着したら、火を入れる直前にお別れの時間が設けられます。
一般的な様式では、炉の前に祭壇を配置して、その上に位牌と遺影を置きます。
僧侶が同行している場合は読経と焼香、居ない場合は焼香だけを実施した後に合掌して見送ります。
火葬が開始されてから完了するまでには、おおよそ40分から2時間ほどを要します。
待機時間中は、専用の控室で待機することが一般的です。
幾らかは時間が掛かるので、喪主は飲み物を手配しておく辺りの気遣いを心がけましょう。
僧侶が同席している場合は、部屋奥の上座へ誘導することも確実に実施しましょう。
骨上げ
火葬が終了したら、参列者は炉の前に移動して骨上げを実施します。実施する際は二人で一膳の箸を持ち、故人と縁が深かった人から順に行います。
足元の骨から登っていくように進めましょう。
拾うべき骨を全て骨上げしたら、最後に喉仏の骨を拾って終了になります。
火葬で言う喉仏は第二頸椎(頸椎部の骨)であり、拾うのは喪主および縁の深い親族であることが一般的です。
第二頸椎は仏が座禅しているかのような形状に見えることから、第二頸椎を最後に骨上げするようになったそうです。
火葬場の仕組み
火葬場は全国にある施設ですが、基本的な構造は全国どの火葬場でも類似しているものです。
棺の大きさによっては対応できる火葬場が近場にない、という事も起こり得るので、火葬場を探す段階にある方は基礎的な知識を身につける必要があります。
火葬炉
火葬炉は、故人や棺の大きさによって標準、大型、小型の3種類を使い分けます。
定義は火葬場毎に異なりますが、標準炉は長さ2m、幅55㎝、高さ50㎝前後であることが多いようです。
これを上回りそうなら大型炉、小さそうであれば小型炉を使うのが一般的です。
ただし大型炉は備えていない所も多いので、火葬場には前もって確認するようにしましょう。
火葬時間を予測する目安として、炉の形式と特徴もご紹介します。現代では台車式、ロストル式のどちらかが多く用いられています。
台車式は燃焼温度が低く、火葬時間は長いが遺骨が多く残りやすいことが特徴です。
ロストル式は燃焼温度が高く、火葬時間は短いが骨が残りづらいことが特徴です。
告別室
棺が火葬炉に入る前に、遺族と故人が最後に顔を合わせられる場所が告別室です。
現代の棺には小窓が設けられている物が多いので、小窓から故人の顔を確認することができます。
衛生的に心配される方もいるかと思われますが、小窓を開けるとアクリル板で仕切ってあるタイプの棺も現代ではあるようです。
喪主や参列者の意向に応じた時間を過ごせるようにしましょう。
炉前室
炉前室とは、シンプルに火葬炉の前にある部屋です。
僧侶による読経や、参列者が焼香を行う場として用いられることがあります。
参列者が数人ほどの少人数である場合、告別室ではなく炉前室でお別れを行う場合があります。
そして、炉前室は火葬炉が廊下から直接見えないようにする役割があります。
燃焼中の火葬炉を直接見ることで遺族が精神的負担を受けないように、炉前室にはドアが設置されていることが一般的です。
控え室
火葬が終わるまでの間、参列者や僧侶の方が待機する場所が控え室です。
喪主や遺族は、飲み物やお茶うけなどを手配して気楽な時間を過ごせるように心がけましょう。
火葬は40分~2時間を必要とする過程なので、故人に関する話で会話を楽しむこともルール上は問題ありません。
火葬のみ(直葬)という選択も増えている
近年では、通夜、葬儀、告別式といった過程を省略した「直葬」という葬儀形式が登場しています。
故人の死亡診断書を受け取った後、火葬場へ直行して骨上げまで済ませることを直葬と言います。
直葬を選択するメリットは、一般的な葬儀に比べて費用が抑えられる事と、長くても半日ほどで終了することです。
葬儀費用は家族葬でも100万円ほどは掛かるケースが珍しくありませんが、直葬では20~30万円ほどで収まるケースがほとんどです。
そして火葬だけで終わるので、遺族や参列者が多忙でも合間を縫って参列に訪れやすいというメリットもあります。
ただし、火葬以外を省略する簡易的な葬儀なので故人と過ごせる時間は少なく、開始から骨上げまでの過程もスケジュール優先で慌ただしく終わる事が多いようです。
簡素すぎる葬儀は遺族だけでなく参列者にも悪印象を与えやすく、場合によってはトラブルの原因になることもあります。
遺族や参列者と相談したうえで直葬を決めることはあっても、早く済ませたいからと直葬を選ぶのは避けた方が無難です。
まとめ
日本は元来土葬が主に実施されていましたが、仏教が伝来してから十数世紀をかけて火葬が広まっていったという背景があります。
火葬許可証や埋葬許可証に関しては無いと手続きが進められないので、許可証の取り方と提出先だけは少なくとも覚えておきましょう。
そして、棺の選び方や控え室での過ごし方などは、知っておくと故人とのお別れを後悔なく済ませられるようにスケジュールを組み立てやすくなる大事な情報です。
今まで火葬場には出向いたことがない人でも、これから年齢を重ねていくにつれて葬儀への参列も増えていきます。
そんな時、火葬場の機能や歴史、仕組みを知っておくと、正しい振る舞いができるかもしれません。

























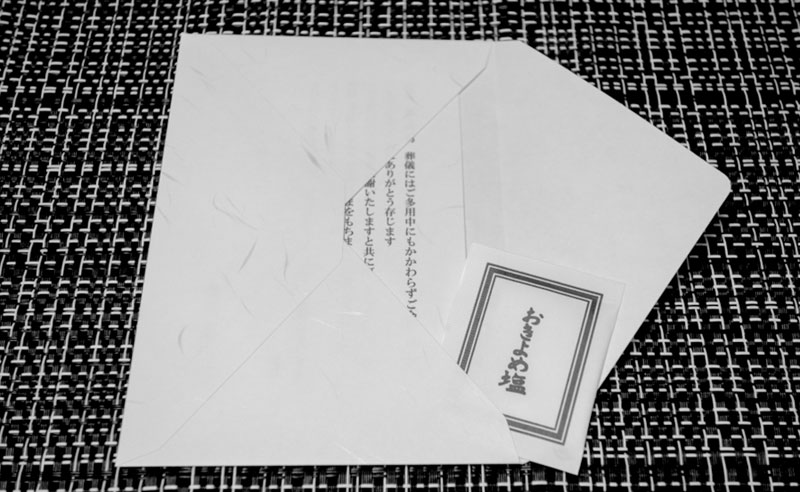


 葬儀・お葬式
葬儀・お葬式 参列マナー
参列マナー 葬儀後
葬儀後 法事・法要
法事・法要 終活
終活 葬儀前(事前相談)
葬儀前(事前相談)























