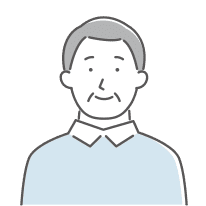納骨する場所
納骨とは、火葬されて骨になった故人を骨壺に収め、お墓に納めることを意味します。
納骨される場所は、先祖代々のお墓であることが多いですが、近年はライフスタイルや価値観の変化から、必ずしもお墓に納骨するとは限らなくなってきました。
ここではお墓をはじめとする納骨する場所についてご紹介します。
所有するお墓に納骨する
霊園やお寺など自身が所有するお墓がある場合は、そのお墓に納骨します。
自身が所有するお墓があれば、納骨をする場所には困りません。先祖代々受け継がれているお墓があるならなお良いでしょう。
ただし、自身が所有するお墓ですので、定期的なお参りをして手入れをする必要があります。
お彼岸の時期や、お参りをしたいと感じた時にお参りすることを心がけましょう。
合葬墓と納骨堂に納骨する
合葬墓は、ひとつの同じ場所に不特定多数の人々の遺骨を埋葬し、墓碑や石塔などを立てることによって供養を行うという供養形態です。
かつては、身寄りのない方のお骨を「無縁仏」としてまとめて合葬することがありました。
最近では少子高齢化の影響で、承継者問題や家族に迷惑をかけたくないという思いから、合葬の重要性が見直されています。
故人を供養するために遺骨を骨壺に入れて安置しておくための施設や設備を納骨堂と言います。納骨堂には様々な形状があり、形状によって費用もまちまちです。
散骨や手元供養という方法も
現代においては、納骨をせずに、故人の遺骨を海や山など、故人のゆかりのある場所などに撒く「散骨」という方法もとられるようになってきました。
また、「手元供養」という方法も近年多くの人に選ばれています。これは、納骨をする代わりに文字どおり遺骨を遺族の手元に置いて供養することです。
遺骨をお墓などに納めた上で、遺骨の一部をペンダントなどに加工する場合もあります。
納骨を実施する時期
納骨を行う時期は、宗教によって異なります。ここでは、仏教、神道、キリスト教に分けて、それぞれの納骨の実施時期についてご紹介します。
仏教では四十九日法要で
仏教では人が亡くなって以降、七日ごとに閻魔(えんま)王などの冥府の裁判官による裁判が行われると考えられています。
亡くなった方の徳を高め、少しでも良い世界へと導いてもらえるようにするために、初七日、二七日、三七日、と七日ごとに親族が集まって法要を行います。
また、人が亡くなってから四十九日目に最後の裁判が行われるとされています。仏教内の宗派によって考え方は多少異なりますが、ほとんどの仏教には最後の裁判が終わると人はあの世に行ってしまうという考えがあるため、四十九日の法要をもって「忌明け」とし、納骨を実施します。
神道
神道においては、火葬をして骨上げをしたあと、その日のうちに墓地などの納骨をする場所に向かい、納骨を行います。
お墓をまだ建てていないなどの理由で納骨ができない場合は、五十日祭か一年祭を目安として、納骨を行います。納骨の際に「埋葬祭」という儀式を行うことが特徴です。
神道においては、お寺のように敷地内にお墓を建てるということをしません。一般的な霊園に埋葬し、神主の立ち会いのもとで、納骨式(埋葬祭)を行います。
神主によってお祓いが行われた後、祭詞をあげて玉串奉奠(たまぐしほうてん)を行います。これは仏式の焼香に相当するもので、神主と参列者全員が行います。
キリスト教
キリスト教は大きく分けてカトリックとプロテスタントの二つの宗派があります。カトリックの場合は追悼ミサの翌日、またはその1か月後のミサの際に、プロテスタントの場合は亡くなってから1か月後に行われる「召天記念日」という記念式の際に納骨式を行います。
キリスト教における「死」の概念は、日本の仏教や神道のそれとは異なります。
カトリックでは、故人の生前の行いによって、死後に行く世界が決まるとされています。一方、プロテスタントでは、生まれながらの罪人である人類は、キリスト教を熱心に信仰することで天国に行かれるとされています。
納骨に必要な費用
納骨をするには、墓石を動かしてから、お墓の下にある納骨室である「カロート」を開け、その中に骨壺を入れなくてはなりません。
納骨後も、墓石に(ある場合は墓誌にも)故人の戒名と没年を彫刻する必要があります。これらの作業は主に石材店に依頼して行います。
料金は石材店によって異なりますが、一般的には墓石の移動やカロートの開け閉め作業に対する「作業代」は1万5千~3万円、墓石への「彫刻料」は3万~5万円程度となっています。
納骨式を実施するまでの流れ
納骨式を行うにあたっては、様々な手配や書類の用意が必要となります。納骨式に参加する親戚や故人の友人などの人への連絡も必要です。
ここでは、納骨式の手配の進め方や必要な書類について、および納骨式に呼ぶ人の範囲についてご紹介します。
手配の進め方と必要な書類
納骨および納骨式は四十九日の法要の際に行うことが多いので、お寺などに法要を依頼する場合は早めに相談して、日程を決めましょう。日時の相談の際に、卒塔婆を立てるかどうかも決めることができます。
また、前述のとおり、納骨には墓石の移動やカロートの開閉、お墓への戒名の彫刻なども必要です。同じタイミングで石材店への依頼も済ませておきましょう。
必要な書類としては、「埋葬許可証」と墓地の「利用許可証」の2つが挙げられます。埋葬許可証は、火葬後に骨壺と一緒に受け取ることができます。
墓地の管理事務所で利用許可証の手続きをする際には、印鑑も必要になるので忘れないようにしましょう。
家族や親族、近しい友人を呼ぶ
は、事前にお店の予約を済ませることも忘れてはいけません。
納骨式に呼ぶ人の範囲については、特に厳格に決まっているわけではなく、遺族とその親族だけで行うことも少なくありません。誰を呼ぶかは、遺族の方の意向で決めると考えて差し支えありません。
納骨式当日の流れ
ここでは、納骨式の一連の流れについてご紹介します。実際に納骨式をする際に困らないように、どのようなことが行われるかを理解しておきましょう。
喪主のあいさつ
お供え物を供え終えて、納骨式を執り行う準備が整ったら、喪主が遺族の代表として、参列者の方々へ向けての挨拶をします。参列したことへのお礼と遺族の近況を報告します。会食がある場合、そのことも忘れずに伝えるようにしましょう。
納骨、読経・焼香
納骨が終わった後に、僧侶による読経が行われ、その間に遺族や参列者が焼香を行います。お墓で行う場合は墓前にて行いますが、寺院に移動して屋内で行う場合もあります。
遺骨をお納めする際、僧侶は「納骨経」と呼ばれる故人を供養するためのお経を唱えます。
遺族および参列者は僧侶の指示に従って焼香を行います。喪主が最初に焼香をし、遺族、知人・友人の順に焼香します。
会食
納骨式が終了した後、僧侶を含めた参加者全員で会食を行います。全員が会場に移動し、会食の準備が整い次第、故人のご位牌の前にお酒の入った杯を用意した上で、喪主は再びあいさつをします。
この時のあいさつはなるべく手短にしましょう。会食が終わる際も、喪主は挨拶を行います。その後、返礼品である引き出物を参列者に手渡して解散となります。
納骨式でのマナー
ここでは、納骨式におけるマナーについてご紹介します。当日着用する服装についてはもちろんのこと、参列する方は香典や御供物料のことにも気を配る必要があります。
服装
納骨式における服装は、納骨式が行われる時期によって変わります。
四十九日より前に納骨される場合は、喪服を着用します。通夜や葬儀の際に着用したものと同様のもので構いませんが、その場合は、焼香の際に香炉の灰などで汚れていることもあるため、納骨式が行われる前に改めてしっかりチェックしておき、汚れが目立つ場合はクリーニングに出しておく必要があります。
四十九日以後に納骨をする場合は、平服が一般的です。平服といっても、派手な色や柄物の服ではなく、グレーや黒といった暗めの色の服で統一するのがよいでしょう。
男女ともに、ダークスーツを着用するのが無難であるといえます。
香典や御供物料
納骨式の際には、香典の表書きにも気をつけたいものです。四十九日以前の表書きは「御霊前」としますが、四十九日を過ぎると故人の魂はあの世に行ってしまうという仏教の教えから、四十九日以降の法要の際は「御仏前」か「御佛前」という表書きに変わります。
法要の際の香典は薄墨ではなく普通の黒墨を使用します。
納骨式の際、お供え物は遺族の方が用意します。そのため、参列する方は「御供物料」という形で現金をお納めすることが一般的です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。この記事では、納骨する場所や時期と、費用、納骨式の流れ、そしてマナーについてご紹介しました。納骨式は亡くなった人のお骨を納めるという非常に重要な儀式です。
この記事で納骨式について学んだことを、ぜひ役立ててくださいね。























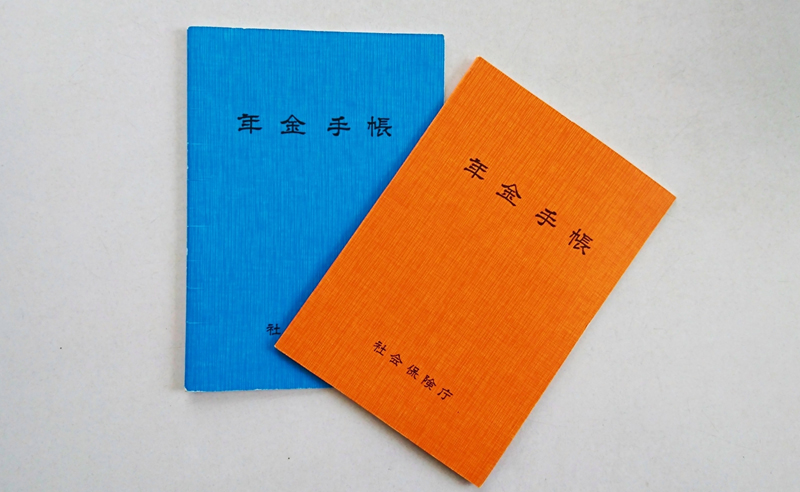



 葬儀・お葬式
葬儀・お葬式 参列マナー
参列マナー 葬儀後
葬儀後 法事・法要
法事・法要 終活
終活 葬儀前(事前相談)
葬儀前(事前相談)