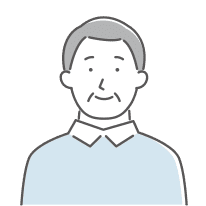喪中はがきとは
喪中はがきをなぜ出すのか理解していないと、投函時期や送付相手を誤ってしまう可能性があります。
ここでは、喪中はがきの基礎知識と、喪中の範囲、適切な投函時期について解説します。
喪中はがきは年賀状の代わりの挨拶状
喪中はがきは、正式には「年賀欠礼状」といい、近親者が亡くなったために、新年の挨拶を控えることを事前にお知らせするための挨拶状です。
喪中とは、故人の死を悼み、慶事に関わることを避ける期間のことです。現代にも残っている風習として、近親者が亡くなった日から1年間は新年の挨拶や結婚式などのお祝い事を控えるのが一般的です。
喪中となる親族の範囲
喪中となる親族の範囲は、一般的には親、配偶者、子である1親等と、兄弟姉妹、祖父母、孫である2親等とされています。
3親等にあたるおじやおば、甥や姪、曾祖父母は喪に服す必要はありませんが、同居や親しい間柄だった場合などは喪に服す場合もあります。
喪中はがきを出す相手
喪中はがきは、基本的に毎年年賀状のやりとりをしている全ての方に送ります。その他にも、故人の友人、葬儀に参列してくれた方、それぞれにも感謝の言葉などを添えて喪中はがきを送ります。
仕事の関係者にも喪中はがきを送りますが、昨今はプライベートで付き合いがない相手に対しては、必要以上に気を遣わせないために普段通り年賀状を送る場合もあります。
喪中はがきを投函する時期
喪中はがきは新年の挨拶を控える旨を伝えるものであるため、先方が年賀状の準備を始める前に届くように送ります。
よって11月中か、遅くても12月の上旬までに投函しましょう。
喪中はがきに関するマナー
マナーを守らず喪中はがきを送ってしまうと、相手に失礼な印象を与えてしまう恐れがあります。ここでは知っておきたい喪中はがきのマナーを解説します。
使用するはがきと切手
喪中はがきに官製はがきを使う場合は、「胡蝶蘭」のデザインを選びます。私製はがきを使用する場合は、「弔事用63円 普通切手花文様」を選びます。
句読点は使わない
儀礼的な挨拶状には句読点は用いません。もともと日本語に句読点はありませんでしたが、明治以降、文章の区切りを分かりやすくするために補助としてつけられるようになりました。
よって、わざわざ句読点をつけた文を送ることは、先方に対して「読みやすいようにしてあげる」という意味を持ち失礼であるという考えから、挨拶文に句読点を用いることはマナー違反とされています。
同様の理由から、行頭の1字下げも行いません。喪中はがきだけでなく、年賀状や暑中見舞いなどの挨拶状では句読点は使用しないようにしましょう。
忌み言葉は使わない
喪中はがきでは、死をストレートに表す「死去」「死亡」といった表現や、「重ね重ね」「度々」など不幸が続くことを連想させるような重ね言葉は避けましょう。
また、「拝啓」「敬具」などの頭語や結語も使用しません。
基本的に添え書きはしない
喪中はがきを書く際、基本的に添え書きは不要です。近況報告などは書かないようにしましょう。中でも、結婚、出産、などの慶事に関する報告を喪中はがきですることは避けなければなりません。
喪中はがきを送るタイミングで祝い事を報告したい場合は、「寒中見舞い」で改めて報告するのが良いでしょう。なお、法要出席への感謝の言葉を添えるなど、弔事に関することは添え書きしても問題ありません。
喪中に年賀状が届いてしまった場合
喪中はがきは、あくまでも喪に服している人が新年をお祝いする挨拶を辞退することをお知らせするために出すものです。そのため、喪中に年賀状を受け取ること自体はマナー違反ではありません。
もしも喪中に受け取った年賀状へ返事を出したい場合は、「寒中見舞い」で対応しましょう。寒中見舞いは、主に1月8日、地域によっては1月16日の、「松の内」が明けてから出す挨拶状です。
喪中に受け取った年賀状へのお返しとして送る場合は、喪中の連絡が行き届かなかったことをお詫びする文章を添えましょう。また、喪中とは知らずに年賀状を出してしまったことをお詫びしたい場合も、同様に寒中見舞いでお詫びをすると良いでしょう。
喪中はがきの書き方
喪中はがきは、いくつかの決まりを守れば簡単に書くことができます。ここでは喪中はがきを書く際におさえておきたいポイントを紹介します。
記載する内容
喪中はがきは縦書きで書くのが一般的です。前文の挨拶では、新年を祝う意味を持つ「年賀」という言葉は使わず、「新年」や「年始」、「年頭」といった言葉で書き始めます。
喪中はがきに盛り込むべき内容は以下の6点です。
1. 年賀欠礼の挨拶
2. 故人の情報(故人の名前、いつ、数え年の享年、故人との続柄)
3. 今後も変わらぬお付き合いを願う言葉
4. 日付(正確な日付ではなく「令和〇年〇月」と書くのが慣例)
5. 差出人の情報(住所、氏名)
6. 故人が生前お世話になったことへの感謝の言葉や挨拶
例文
ここでは喪中はがきで使える例文をご紹介します。
・一般的な文例
「喪中につき新年のご挨拶をご遠慮申し上げます
本年〇月〇日に父〇〇が〇〇歳にて永眠いたしました
本年中のご厚情を深謝いたしますとともに
〇〇様にはどうぞお健やかに良いお年をお迎えくださいますよう
お祈り申し上げます」
・故人が複数名の場合の文例
「喪中につき年末年始のご挨拶を慎んでご遠慮申し上げます
本年○月 父○○が○○歳にて永眠いたしました
本年○月 母○○が○○歳にて永眠いたしました
生前のご厚誼を深く感謝申し上げます
なお時節柄一層のご自愛のほどお祈り申し上げます」
まとめ
本稿では、喪中はがきの意味や基本的な書き方、マナーや疑問点についてご説明いたしました。喪中はがきを書くのが難しいと思っていた方でも、基本的なルールとマナーさえ理解しておけば、簡単に書けることがお分かりいただけたと思います。
この記事を参考に、基礎知識やマナーをふまえて喪中はがきを準備し、正しい喪中はがきを送りましょう。
























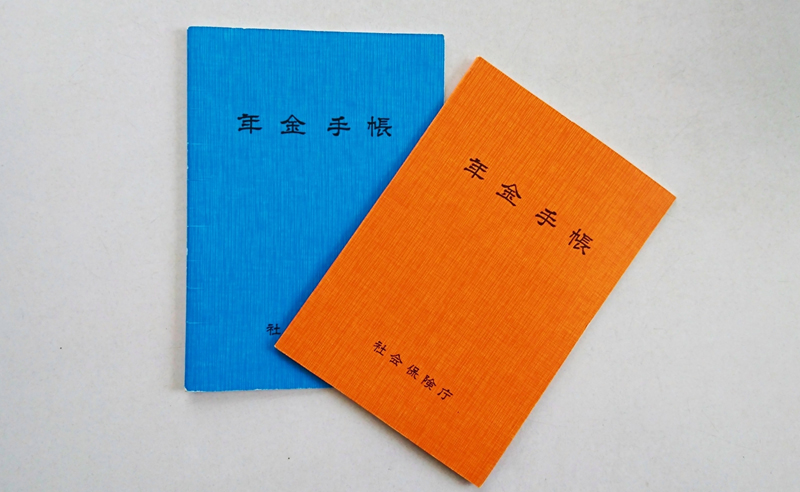


 葬儀・お葬式
葬儀・お葬式 参列マナー
参列マナー 葬儀後
葬儀後 法事・法要
法事・法要 終活
終活 葬儀前(事前相談)
葬儀前(事前相談)