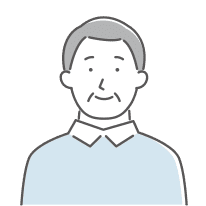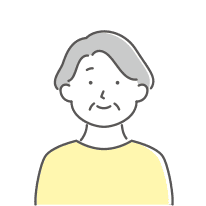忌引きとは
仏教や神道でいう忌引きとは、自分の近親者が亡くなった時に学業や仕事を休んで葬儀や通夜に参列したり、遺族として葬儀の準備を手伝ったりすること、および故人を偲ぶ時間を作ることです。
具体的には、本人から2親等以内、あるいは同居している3親等の方が亡くなられた場合は忌引きに該当します。
参考として、1親等以内には配偶者、(義)父母、子、子の配偶者が該当します。
2親等には(義)祖父母、(義)兄弟姉妹とその配偶者、孫とその配偶者が該当します。
3親等には(義)曾祖父母、(義)伯叔父母、(義)姪・甥、ひ孫とその配偶者が該当します。
なお、近親者や身近な友人などの不幸によって会社や学校を休むことを忌引き休暇といいます。休暇を取れる日数は企業ごとに個別で決める制度となっていますが、一般的には1~10日ほどの間で設定している企業が多いです。
忌引き休暇は故人と自分の続柄に応じて認められる日数が変わる事が多く、基本的には親等が近いほど休暇日数は長くなります。ただし、義理の親族である場合は、親等が近くても休暇期間は短くなる傾向があります。
その他、喪主を務める場合や、自宅から葬儀場までが遠い場合などには規定より長い休暇が認められるケースもあります。
企業が設定している忌引き休暇は故人の葬儀や火葬、それに伴う書類手続きなどを済ませることが主な目的なので、仏教や神道宗教でいう忌引きよりも期間が短めに設定されているようです。
忌引き連絡で伝えるべき内容
会社や学校へ忌引きの連絡をする際は、誰がいつ亡くなった、故人と自分の続柄、自分は参列者か喪主か、通夜から告別式までのスケジュール、不在期間中に連絡できる番号やメールアドレスを伝える必要があります。
喪主かどうか、および故人との間柄に関しては取得できる休暇日数に関連してきます。喪主は会場の手配を始めとして行うべき仕事が多いので、社内規定よりも1~3日ほど長い休暇を認める企業が一般的です。
葬儀のスケジュールを伝える理由は、当日には上司や同僚、先生などが葬儀に参列したり、弔電を手配してくれたりすることがあるからです。弔電は早く着きすぎても遅く着いてもダメなので、葬儀のスケジュールは必ず正しく伝えましょう。
なお、近年では1~2日ほどで葬儀を執り行うコンパクトな葬儀形式も増えてきており、法定休日だけで葬儀を終えられるケースも増えているようです。
とは言え、身内の葬儀があった事は会社へ伝えておくべきです。何かの折に後から発覚するよりも、例えば週明けに出社した時点で知らせておいた方が無難です。
そして、企業によっては、従業員の葬儀には慶弔金が支払われるケースがあります。社内規定がある場合、コンパクトな家族葬や直葬などでも慶弔金をもらえる企業がほとんどです。
忌引き連絡の方法
会社や学校などを身内の不幸によって休む場合、直接顔を合わせて言う、もしくは電話で伝えることがほとんどです。
ただし、状況によってはメールを使う場合もあるようです。
直接会う
一般的に、会社の同僚や上司に忌引き連絡をする際は、出来るだけ相手と直接対面して口頭で連絡することがマナーとされています。
本人が直接出向いて伝えることで礼儀を重んじている印象を相手に持たれやすくなるほか、仕事の引継ぎや必要事項の伝達などが行いやすくなるメリットもあります。
なお、口頭で葬儀の日程や不在になる期間などを伝えた場合、内容を後からメールで送ることが社会的なマナーとされています。
電話
訃報を知ったのが休日や退勤した後だった場合などは、連絡手段として電話を用いることが一般的です。
仕事に関する話ではなく、忌引きは正確に予測できる事でもないので、休祝日でも会社の上司に連絡を取ることは問題ありません。
もし上司本人が不在であれば、家族に言伝をお願いする形でも大丈夫です。
ただし、深夜もしくは早朝などは電話を避けてメールを用いるべきです。
メール
訃報を知ってから葬儀までに時間的な余裕がない、もしくは精神的なショックで電話や外出を控えたい時などは、忌引き連絡をメールで実施しても問題はありません。
ただし、状況や気分が落ち着いたら電話もしくはFAXなどで改めて連絡を行いましょう。
なお、メールでの忌引き連絡は一般的にマナー違反ではありませんが、会社や人によっては失礼だと思われる可能性があります。
送信してから読まれるまでに時間が掛かりやすいというデメリットもあるので、特に理由がなければ電話や対面で連絡することをおすすめします。
忌引き連絡する際のマナー
ここでは、実際に忌引き連絡を行う上で伝えるべき事や、前もって知っておくべきマナーをご紹介します。
直接会う場合
相手に直接会って話ができる場合、上司に対しては休暇を申請したい事、申請する上で必要な書類はあるか、休暇期間内に用意してくるべき書類はあるか等を必ず聞くようにしましょう。
会社によっては故人の死亡診断書や火葬許可証などを要求されることがあります。
そして、特に中小企業は忌引きに関する規定を設けていないことも考えられます。
規定がない場合は有給休暇を充当したり、欠勤扱いとはしないが休暇中は無給扱いにしたりするなど企業によってルールは異なるので、忌引き休暇に関する決まり事は必ず確認するようにしましょう。
電話の場合
電話で忌引き連絡をする場合は、会社の始業時間から終業時間までに連絡を入れることが一般的なマナーです。
会社に人が居ないタイミングで訃報を知った場合は始業時間まで待つか、あるいはメールで連絡することが一般的です。
メールの場合
メールで連絡をする場合、タイトルを「忌引き休暇願い」や「訃報のご連絡」として要件を分かりやすくする事が大切です。既に葬儀スケジュールが分かっているなら、タイトルに休暇の申請日数を併せて書いておくと一層良いです。
そして、葬儀関連の要件をメールで伝える際は、頭語や季節の挨拶を省いて最初から本題に入るようにします。電話や口頭で伝えてから形式的に送る場合と、取り急ぎメールで送る場合がありますが、どちらの場合でも書くべき内容はほとんど同じです。
忌引き連絡をどこにするか
忌引きで会社や学校を休む際は、学校や会社を始めとして多方面に連絡を行う必要があります。ここでは、忌引きの連絡を行うべき場所や知っておくべき知識をご紹介します。
学校
忌引きで学校を休む場合、まずは忌引きに関する規定があるかを確認する必要があります。
規定を設けている学校であれば、忌引きで休んだ日数を実質的に出席した日として数えてくれる所がほとんどです。
ただし、規定が無い学校だと、休んだ理由に関わらず通常の欠席として扱われます。喪に服す長さとそれまでの欠席数次第では、進級に必要な出席日数に届かなくなることがあり得るので注意が必要です。
なお、学校へ忌引きの連絡をする場合には、必ず親が伝えることがマナーとされています。子供が小学生であれば連絡帳に必要事項を書いて渡す形で良いですが、基本的には電話で伝えることをおすすめします。
会社
会社や学校を身内の不幸によって休む場合、忌引き休暇の申請や社内規定に関する確認などは、必ず直属の上司に話すようにします。そこから総務部や人事部などにも連絡するよう指示されたら、適宜伝達するようにしましょう。
そして、忌引きで休むことを許可された場合は、同僚や上司などに仕事の引継ぎをお願いする必要があります。
同僚の方には休む期間や葬儀会場の住所、スケジュール、自分が喪主かどうかを伝えるとともに、引き継ぎたい仕事内容と商談なども忘れずに共有しておきましょう。
なお、引継ぎが難しい取引先がある場合は自分で個別に断りの連絡をする必要があります。
取引先
一般的に、取引先への忌引き連絡は上司や同僚が代行することがマナーとされており、忌引き休暇を取る本人からは行わないものです。
もし本人から連絡すると、話した内容にかかわらず香典を要求している、もしくは参列するように促している形になってしまうので注意が必要です。
ただし、引継ぎが難しい取引先とのアポイントを忌引きでキャンセルする場合には、当事者が連絡する必要があります。
アルバイト先
アルバイトやパートの方が忌引き休暇を申請する場合、まずは社内規定を確認する必要があります。
原則として正社員とアルバイトは社内規定が異なるので、会社によっては、正社員は有給扱い、パート・アルバイトは無給の休日扱いとなっていることもあります。
実際に申請する際は、直属の上司に相談することが一般的です。
まとめ
忌引き連絡を行う際は、葬儀スケジュールや葬儀場の場所、亡くなった人と自分の間柄などを必ず説明するようにします。学校、職場は両方とも忌引き休暇に関する規定が異なったり、場所によっては無かったりするので必ず確認するべきです。
学校や一部の職場に関しては、事前に申請しておかないと手続きが通らず、欠勤・欠席扱いとされてしまう場合もあるので注意が必要です。
もし忌引きの知らせを行う必要が出てきた時は、当記事で紹介した知識やマナーを参考にして、少しでも不安のない状況で葬儀や通夜に参列できるように心がけましょう。
























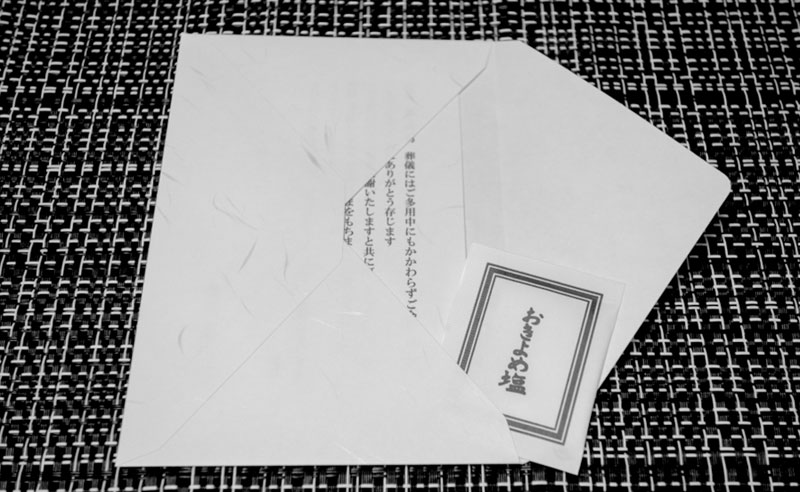


 葬儀・お葬式
葬儀・お葬式 参列マナー
参列マナー 葬儀後
葬儀後 法事・法要
法事・法要 終活
終活 葬儀前(事前相談)
葬儀前(事前相談)