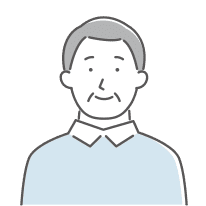焼香とは何か
焼香とは、死者に対してお香を焚いて拝むことです。お香のなんともいえない良い香りは、仏の住む浄土を表現しています。
お香の香りは隅々まで広がり全ての人に平等に届くことから、仏の慈悲を表していると言われています。
仏教においては、ある悩みを解決するために香が焚かれ始めました。その悩みとは、仏陀が仏教を説いていた2000年前のインドにまでさかのぼります。
当時のインドにおいて、仏陀の説法に耳を傾けるのは主に最下層の肉体労働者や乞食が中心でした。彼らを取り巻く衛生環境は極めて悪く、体臭や悪臭を漂わせている者が多かったのです。
その臭いにはさすがの仏陀も閉口し、悪臭を消すために香を焚くという行為を導入しました。その後、香を焚くという行為は仏教に深く根付いていくことになるのです。
そもそもインドでは、仏教が普及する以前から香木として利用される白檀(びゃくだん)を焚く習慣がありました。
それをのちに仏教が取り入れたということになります。
焼香は一見すると故人に香を手向ける行為に見えますが、本来は参列者自らの心と体の穢れを落として、清らかな心で故人に祈りを捧げるための下準備という意味を持つのです。
通夜とは何か
通夜とは仏教における葬儀前の儀式のことです。本来は、家族や近親者が線香やろうそくの火を絶やさないよう、夜通し故人との別れを偲んで行う儀式であり、一般の参列者は翌日の昼間の告別式に出席していました。
しかし時代の変化とともにお通夜も変化し、仕事の関係者や近所の方々が参加しやすいよう、18時から19時頃に僧侶の読経が始まるようになりました。
抹香を用いた焼香の作法
焼香はどのように行えば良いのでしょうか。以下では抹香を用いた焼香の作法と手順をご紹介します。
立礼焼香
一般的な葬儀ではこの立礼焼香が行われます。立礼焼香は立ったままで焼香をします。手順は以下の通りです。
1. 遺影に向かい一礼をして合掌します。数珠を持参しる場合は左手に持ちましょう。
2. 抹香を右手の親指・人差し指・中指の三本でつまんで目の高さまで掲げ上げます。
3. 掲げ上げた抹香を少しずつ静かに香炉の中に落とします。宗派によって異なりますが、これを1~3回行います。
4. 再び合掌した後、遺影に向かい一礼します。その後、遺族と僧侶に一礼して席に戻ります。
座礼焼香
小規模な会場や和室で葬儀を行う場合、椅子を用意することは少なく、座ったままでお焼香をします。
これを座礼焼香と言います。基本的に順番になったら焼香台まで進んでお焼香するという立礼焼香と同じですが、自分の席から焼香台までの移動方法が独特です。
この移動を「膝行(しっこう)・膝退(しったい)」と呼びます。具体的な移動方法は以下の通りです。
1. 座った姿勢で、かかとをあげてつま先立ちをします。
2. 手を軽くついて身をかがめ、膝を交互に運んで進みます。
3. 戻る際は前向きのまま同様に下がり、最後に立って席に戻ります。
回し焼香
葬儀を自宅で行う場合、家の広さの関係上、立礼焼香などを行うことが難しいケースもあります。
その場合はお盆に香炉と抹香を乗せ、それを回してお焼香をする回し焼香を行います。具体的な手順は以下の通りです。
1. 隣の人から香炉と抹香を乗せているお盆が手元に回ってきたら、軽く会釈をして受け取ります。
2. お盆を自分の前に置き、遺影に向かい一礼をしてからお焼香をします。
3. 合掌し、一礼します。
4. お盆を隣の人に回します。
線香を用いた焼香の作法
抹香を用いた焼香だけではなく線香を用いた焼香もあります。
ここでは線香を用いた焼香について解説します。
立礼焼香
線香を用いた立礼焼香の手順は以下の通りです。
1. 遺族と僧侶に一礼し、焼香台の少し前まで歩きます。
2. 遺影を見てから、焼香台の近くまで進んで合掌をします。
3. 左手に数珠を持ち、右手に線香を取ります。
4. 右側のろうそくから線香に火をつけ、左手で線香をあおいで火を消します。
5. 他の人が立てた線香よりも、少し離して線香を立てます。
6. 焼香を終えたら再び合掌し、少し後ろに下がって遺族や僧侶に一礼をして席に戻ります。
座礼焼香
線香を用いた座礼焼香の手順は以下の通りです。
1. 次の順番の人に会釈をしてから、中腰で祭壇へと進みます。
2. 座布団の手前で一度座り、遺族と僧侶に一礼し、さらに祭壇の遺影に向かって深く一礼します。
3. 膝をついたまま座布団の上まで移動し、そこで正座をして、線香を右手に取ってろうそくの火をつけます。
4. 左手で軽くあおいで線香の火を消します。この時、息を吹きかけて火を消すことや、左手に線香を持ちかえることは厳禁です。
5. 先に供えられている線香から、少し離して線香を立てます。
6. 数珠を左右の手にかけて合掌します。
7. 膝をついたままの姿勢を保ちながら、座布団から降りて祭壇の前から下がり、遺族に一礼をして席に戻ります。
仏教派ごとの焼香の作法
ここまで焼香の基本的な手順を解説してきましたが、宗派ごとに作法が異なります。
以下では各宗派の焼香の作法を解説します。
浄土宗
浄土宗では、お焼香の回数に特に決まりはありません。線香の場合は1本立てることが多いようです。線香を折って横に寝かせる「寝線香」にすることもあります。
浄土真宗(本願寺派)
浄土真宗(本願寺派)では焼香は1回のみで、香を額に押しいただきません。
これには「香をお供えする」という意味があります。また、焼香前に合掌はせず、線香は立てずに2つまたは3つに折り、寝かせた状態で供えます。
浄土真宗(大谷派)
浄土真宗(大谷派)では焼香は2回で、香を額に押しいただきません。線香は、本願寺派と同様に立てず、2つまたは3つに折りにして寝かせた状態で供えます。
真言宗
真言宗では焼香は3回です。この3回という数字には諸説あり、空海の教えである三密(身・口・意)に通じるという説や、仏教の三宝とされる「仏・法・僧」に捧げるためという説もあります。線香は3本立てます。
天台宗
天台宗では焼香の回数に特に決まりはありませんが、通常1回か3回焼香をします。線香は3本立てます。
曹洞宗
曹洞宗における焼香は2回ですが、1度目は1つまみの香を額のあたりに押しいただいて焚き、2度目は香を額に持って行かずに焚きます。
1度目に焚く香を「主香」といい、2度目に焚く香を「従香」といいます。線香は1本立てます。
臨済宗
臨済宗における焼香は、香を額に押いただかず1回の場合が多いですが、3回行うこともあります。
また、曹洞宗のように、1度目は香を額に押しいただいて、2度目は押いただかずに香をひとつまみして焼香することもあります。線香は1本立てます。
日蓮宗
日蓮宗における焼香は特に決まりはありませんが、1回もしくは3回行うことが多いようです。また、信徒や参列者は1回で僧侶は3回というところもあります。線香は1本立てます。
仏教以外における通夜の作法
焼香が行われるのは仏式の葬儀のみです。それでは仏教以外の宗教では焼香の代わりにどのようなことを行っているのでしょうか。
ここでは神道とキリスト教におけるお通夜の作法をご紹介します。
神道
神道の拝礼では玉串を奉奠(ほうてん)します。玉串とは榊(さかき)の枝に紙垂(しで)という紙片をつけたもので、これを捧げて故人が安らかに眠ることを祈ります。
なお、神道では、弔事の際の拍手は「しのび手」といって音を立てずに行います。玉串を奉奠する作法は以下の通りです。
1. 神官に一礼し、玉串を受け取ります。右手は枝を上から、左手は葉先を下から持ちます。
2. 玉串案(台)の前まで進み、一礼します。
3. 玉串の根元が手前になるように、時計回りに90度回します。
4. 左右の手を持ち替えます。
5. 時計回りで玉串の根元を祭壇に向け、玉串案(台)に捧げます。
6. 数歩退いて、2回深く礼をします。(二礼)
7. 2回音を立てずに「しのび手」を叩きます。(二拍手)
8. 再び深く1回礼をします。(一礼)
9. 神官と遺族に礼をして終えます。
キリスト教
キリスト教式では、お焼香ではなく故人に花を捧げる「献花」を行います。この献花は、キリスト教の信者もそうでない方も、故人とのお別れを表すために行います。
また、最近では無宗教の葬儀でも献花が行われることが増えています。献花の手順は以下の通りです。
1. 花が右側にくるように両手で受け取ります。
2. 遺影に向かい一礼します。
3. 根元が祭壇側に向くように、献花台に置きます。
4. 深く一礼します。(信者の方は十字を切ります。)
5. 聖職者(神父・牧師)や遺族に一礼して終えます。
まとめ
お通夜における焼香のマナーをご紹介しました。焼香の作法は、宗派によって異なることをお分かりいただけたかと思います。
焼香は、自らの心と体の穢れを落とし、清らかな心で故人の冥福を祈るために行います。そう考えると、焼香をする際は一段と身が引き締まる思いがしますね。





















 葬儀・お葬式
葬儀・お葬式 参列マナー
参列マナー 葬儀後
葬儀後 法事・法要
法事・法要 終活
終活 葬儀前(事前相談)
葬儀前(事前相談)