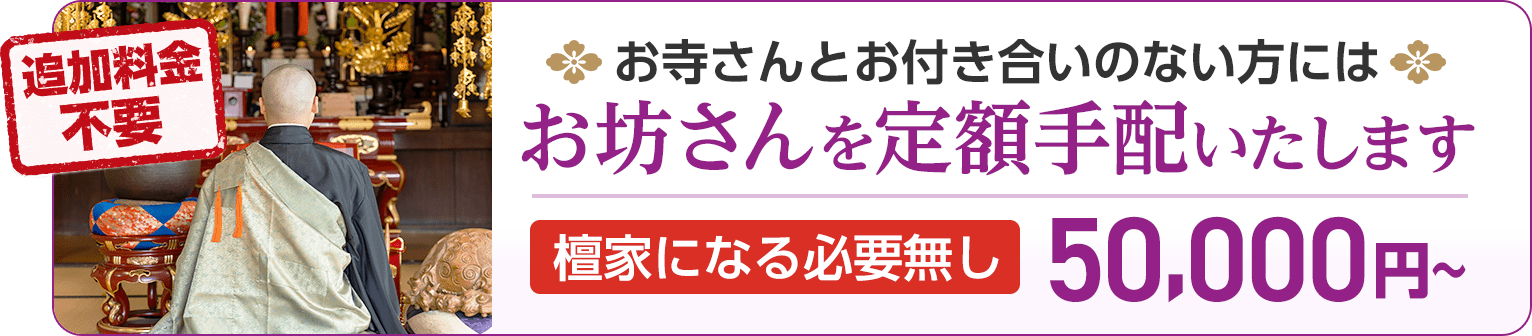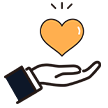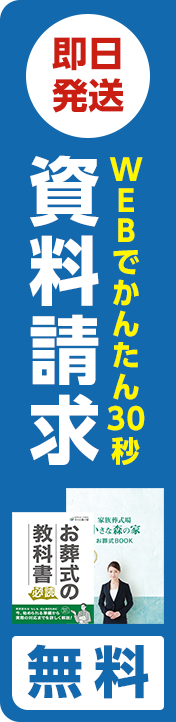喪主とは
喪主とは、遺族の代表者として葬儀や葬式を主催する人のことを指します。
実際の葬儀は葬儀社や僧侶が中心となって進めてくれますが、喪主は葬儀の日時や規模など、葬儀に関わる最終決定権を持つ立場にあります。
喪主は誰がやらなければならないといった法律上の定めはありませんが、故人が遺言状で喪主を指名していた場合はその方が喪主となります。
遺言状で特に指名がなかった場合、基本的には血縁関係の優先順位に則り、わだかまりが残らないよう親族としっかりと話し合って喪主を決めましょう。血縁関係における優先順位は以下のとおりです。
1. 配偶者
2. 故人の長男
3. 故人の次男以降の直系の男子
4. 故人の長女
5. 故人の次女以降の直系の女子
6. 故人の両親
7. 故人の兄弟や姉妹
なお、配偶者や血縁者がいない場合、故人と親しかった友人や知人に頼むのが一般的です。
喪主を依頼できる人がいない場合は、葬儀社が喪主を代行してくれることもあります。
喪主がすべきこと
喪主の仕事は多岐に渡ります。全てを喪主だけでこなすのには限界があるため、必要に応じて役割分担して親族と連携して行うことが重要です。
以下では喪主がすべきことについて、葬儀前、葬儀当日、葬儀後の3つの場面に分けて説明します。
葬儀前
葬儀にあたっては、まずは葬儀社を決めて打ち合わせを行う必要があります。
葬儀社の決め方
喪主が初めにやるべきことは、葬儀社を決めることです。
故人が亡くなられてから葬儀社に連絡するまでにかける時間は、2時間以内が目安とされています。
葬儀社の見積りの比較や検討、連絡した時の応対も含めて親族と慎重に相談し、信頼できる葬儀社を選びましょう。
葬儀社との打合せ
葬儀社と打ち合わせを行い、葬儀の本格的な準備に入ります。
打ち合わせの際は、喪主だけでなく親族にも参加してもらうと良いでしょう。
打ち合わせでは、葬式の場所と規模、予算と見積り、葬儀の日程を詳しく決めます。
日程については、友引の日は「友を引く」という意味で縁起が悪いので避けます。
規模を決める際には、予め誰に訃報を伝えるか決めておき、人数を把握しておきましょう。
予算については金額の分担を親族と相談することも重要です。
葬儀後
葬儀が終わっても喪主がやることは残っています。忌明け法要と香典返しについて解説します。
忌明け法要
亡くなってから49日経つと忌明けと呼ばれ、故人の冥福を祈るための四十九日法要が行われます。
法要を取り仕切るのも喪主の重要な役目です。
まずは忌明け法要を行うお寺と日時を決め、葬儀の参列者に案内状を送付しましょう。
法要が3か月を過ぎてしまうと「三月またぎ」と呼ばれ縁起が悪いため、早めに行うことをおすすめします。
参列者の人数が決まったら、人数に合わせて引出物を準備して当日お渡しします。僧侶への謝礼の用意も忘れずに行いましょう。
香典返し
香典を清算し、お返しするのも喪主の仕事です。
清算もミスがないよう親族と確認しながら行いましょう。
お返しする金額は、いただいた香典の半額が目安とされています。
葬儀当日
葬儀当日の主な仕事は、閉会時の挨拶と葬儀後に行う食事会での対応です。
閉式の挨拶
閉式の際は喪主から挨拶を述べます。事前に挨拶文を書いて手元に持っておくと安心です。
故人の人となりや思い出話を盛り込む場合は、事前に親族に話を聞くとスムーズに書くことができるでしょう。
精進落としでの対応
精進落としとは、葬儀や火葬後に親族やお世話になった方へ振る舞う食事のことを言います。
喪主は精進落としの始まりと終わりにも挨拶を述べます。
また、精進落としが終わった後は、参加者に引き出物を渡します。
さらに、住職が帰る際はお布施を渡すことを忘れないようにしましょう。
喪主としてのマナー
喪主は葬儀を執り行う代表者なので、他の親族とは異なる喪主特有のマナーがあります。
ここでは喪主として守るべきマナーについて、服装と挨拶に分けてご紹介します。
服装
喪服には正式喪服と略式喪服の2種類がありますが、喪主は正式喪服を着用するのがマナーです。
男性の場合、洋装ならモーニングコートが正式喪服です。
モーニングコートとは、黒い上着とベスト、白いワイシャツ、グレー系のストライプのズボンを合わせた服装のことを指します。
和装の場合、黒紋付き羽織袴となります。
女性の場合、洋装なら黒のフォーマルドレスを着用します。和装は黒生地の着物が正式喪服です。
挨拶について
喪主は葬儀の代表者として、参列して下さった方へ挨拶を行います。
その際、重ね言葉は不幸を繰り返す印象を与えてしまうので使わないようにしましょう。
具体的には以下のような言葉が重ね言葉に該当します。
・重ね重ね
・たびたび
・またまた
・再三再四
・次々
・再び
・続く
まとめ
この記事では、喪主の決め方、葬儀前後の役割、喪主を務める際のマナーをご紹介しました。
喪主の仕事が多岐に渡ることに驚かれた方もいらっしゃるでしょう。
もし今後喪主を務める機会があれば、1人で全てをこなそうとせず、この記事を参考にしながら親族と協力して準備を行ってみてください。





















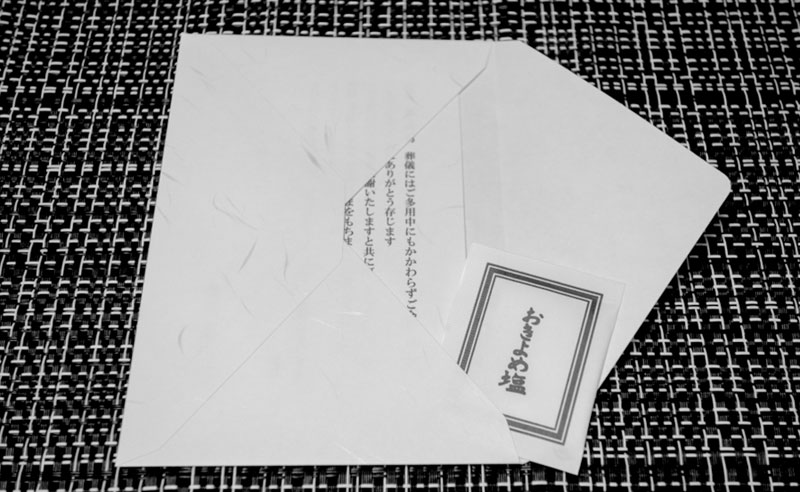


 葬儀・お葬式
葬儀・お葬式 参列マナー
参列マナー 葬儀後
葬儀後 法事・法要
法事・法要 終活
終活 葬儀前(事前相談)
葬儀前(事前相談)