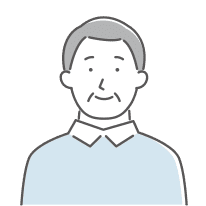法要とは
本来の法要の意味は仏教の行いそのものでした。
しかし時代の流れとともに意味が変わり、今日では亡くなった人に関する行事のことを法要や法事と呼ぶようになりました。
以下では言葉の意味の詳細を解説します。
本来の意味はお釈迦様の教えを知ること
お釈迦様の教えである「仏法」の意味について学ぶことが、法要という言葉の本来の意味です。
これに対し、仏法を世の中に広めるために開かれていた、「法会(ほうえ)」や「斎会(さいえ)」などの行事のことを法事と言います。
故人の冥福を祈る儀式
我が国における法要・法事が故人の成仏を祈る儀式にあたる「追善供養」になったのは、江戸時代あたりからと言われています。
現代でも法要・法事の目的は変わりません。
僧侶にお経をあげてもらって故人の成仏を願い、親族で集まり食事会を催すことが故人への供養になるとされています。
法要と法事は同じ意味で用いられている
法要と法事は、どちらも故人を偲ぶ儀式を指す言葉として広く使われています。
しかし厳密には両者の意味は異なり、法要は故人の供養のために僧侶にお経をあげてもらうこと、法事は法要を含めた親族での食事会など行事全体のことを指します。
法要を行う時期
お経をあげて故人の成仏を願うことを「追善供養」といいます。
毎日お仏壇にお経をあげることも、四十九日や三回忌といった特定の時期に行う法要も、いずれもこの追善供養です。
決まった時期に行う法要について、以下で解説します。
七日ごと四十九日まで行う「忌日法要」
告別式・火葬と同時に執り行われることが増えてきた「初七日法要」や、忌明けとなる「四十九日法要」は、一度は耳にしたことがあるかと思います。
七日ごとに四十九日まで行う法要を「忌日法要」と言いますが、これらは亡くなった人を極楽浄土へ導くことが目的です。
近年では、初七日と四十九日のみ法要を行い、その他の忌日法要は親族でお線香をあげる方が増えています。
決められた年の命日に行う「年忌法要」
忌日法要を終えて極楽浄土へたどり着いた故人がご先祖様・神様になるための法要を「年忌法要」といいます。
亡くなってちょうど1年目に営む「一周忌」に始まり、2年目、7年目、13年目、17年目、23年目、27年目、33年目に行います。
1年目の「一周忌」と2年目の「三回忌」に関係者を集めて法要を行うのが一般的です。
法要前日までの準備
告別式・火葬と同時に行われる初七日を除くと、親族以外に関係者を招くことがある法要は「四十九日」「一周忌」「三回忌」の3回です。
親族・関係者が集まる法事を行う場合には、遅くとも法要の2ヶ月から準備を進める必要があります。
以下では法要までに必要な準備について解説します。
日程・会場・招待客を決める
法要を行う場合にまず行う必要があるのは、法要の日程決めです。
法要は土日祝日に行う場合が大半です。
場合によっては先々の予定まで埋まっている可能性があるので、まずはお寺と日程と会場について打ち合わせをすることをお勧めします。
なお、法要は一般的に親族のみで行いますが、故人の生前の知人・関係者を招待しても問題ありません。
招待リスト作成・案内状送付
知人・関係者へ法要を案内すべく案内状を送付します。
故人との関係ごとに招待リストを作成して、まとめて案内状を送付するとスムーズでしょう。
引き出物・会食の手配
法要で香典・お供え物を戴いた場合には、引き出物を準備するのがマナーです。
葬儀の場合と異なり、法要の返礼品は消え物以外でも問題ないとされています。
以前は法要の後の会食といえば精進料理が正式とされていましたが、近年では形式にはこだわらない方も増えています。
ただし、鯛や海老といったお祝い事でよく出される食材は含まないようにしましょう。
法要当日の流れと進め方
施主・親族は参列者の対応のため慌ただしい時間もありますが、故人を偲ぶ気持ちを大切に、できるだけスムーズに法事が進むように努めましょう。
以下では法要当日の流れをご紹介します。
施主による出迎えと挨拶
まずは参列してくださった方々を出迎え挨拶する機会があります。
親族関係者は、できるだけ早めに準備を済ませて参列者を迎え入れましょう。
香典や供え物は受付を設けて受け取る場合もあれば、直接手渡しでもらうこともあります。
戴いた香典とお供えは御仏前にお供えします。
僧侶による読経と法話
御仏前に、故人と関係が近い順に上座から着席していきます。
参列者が着席し終えたことを確認してから、施主は僧侶・参列者に挨拶を述べます。
その後読経が始まりますが、お経の本が参列者にも配られ、僧侶と共に唱和する場合があります。
読経とご焼香の後に法話を拝聴し、施主のお礼の挨拶で法要は終了となります。
会食から閉会まで
参列者を会食会場まで案内し、お斎(おとき)と呼ばれる会食が始まります。
親族が集まるため、近況や世間話をしてしまいがちですが、故人を偲ぶ時間であることを忘れてはいけません。
最後に施主が参列者の方々へのお礼の挨拶を述べてお開きとなります。
法要に参列する際のマナー
次に、法要に参列する際のマナーをご紹介します。
葬儀と法要とでは細かな作法に違いがあります。
親族に対して失礼にあたることをしないためにも、今一度正しい法要のマナーを確認しておきましょう。
持参するもの
法要に参列する際はお供え物と数珠を持参しましょう。
本来はお供え物としてお線香や和菓子を渡していましたが、近年ではお線香代として現金を渡すことが一般的です。
お供え物として物品を渡す場合には、「消え物」であること、また名前を記載した「のし紙」を添えることに注意しましょう。
数珠は仏様との縁を繋ぐための仏具です。
法要の場では「略式数珠」と呼ばれる安価な数珠でも構いません。
数珠は法要に必ず必要な物ではありませんが、一般的なマナーとして忘れずに持参したいところです。
服装について
法要にする際の服装は、何回目の法要かによって着用すべきものが異なるため注意が必要です。
忌日法要では「四十九日」まで、年忌法要では「三回忌」まで、通夜・葬儀と同じ黒の喪服を着用します。
喪服には「悲しみに寄り添い身を慎みます」という意味があり、三回忌までの法要に参列する際には、親族はもちろんのこと参列者も喪服を着用するのがマナーです。
法要の服装は、七回忌以降であれば平服でも構いません。
法要は、回を重ねるごとに近親者のみで執り行われるようになります。
招待された場合は、ダークトーンの服装を選び、靴やバッグなどの小物も地味なものを選びましょう。
まとめ
法要・法事は故人を偲ぶ機会であると同時に、仏様の教えや命の尊さを知る機会でもあります。
厳粛な気持ちと最低限のマナーを持って、法要・法事に参列するようにしましょう。






















 葬儀・お葬式
葬儀・お葬式 参列マナー
参列マナー 葬儀後
葬儀後 法事・法要
法事・法要 終活
終活 葬儀前(事前相談)
葬儀前(事前相談)