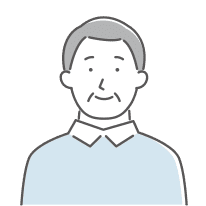喪服とは
葬儀や法事など、弔事の席に着ていく服装を「喪服」と言います。近しい人を亡くした際に「喪に服す」という言葉を使いますが、喪服はこの言葉に由来していると言われています。
元々、喪服は遺族が着る服を指していましたが、近年では葬儀の参列者も弔意を表す意味で喪服を着用するのが一般的です。
なお、喪服と似た言葉に「礼服」があります。礼服とはあらゆる冠婚葬祭に着る服の総称なので、喪服は礼服の中の一つの種類となります。
喪服の種類
続いて喪服の種類について解説します。喪服というと全体的に黒い配色の服というイメージがあると思いますが、主に以下の3種類に分類されます。
自分の立場を考えて、正しい喪服を着用することが重要です。
正喪服について
格式が最も高い喪服が正喪服です。
正しい喪服という意味で「正」の文字が付いています。
男性の場合であれば和装やモーニングスーツ、女性であれば和装やブラックフォーマルが正喪服に該当します。
正喪服は誰もが着用して良い訳ではなく、基本的に葬儀の主催者である喪主や親族が着用します。
しかし、近年ではこの正喪服を実際に着用する方は少なくなってきています。喪服の簡略化が進んで世の中に浸透していることが主な理由です。
多くの葬儀では、主催者側であっても正喪服ではなく、続いてご紹介する準喪服を着用する方が一般的です。
準喪服について
一般的な喪服として広く着用されているのが準喪服です。男性であればブラックスーツ、女性であればブラックフォーマルが準喪服に該当します。お通夜やお葬式、法事など、あらゆる弔事で通用する喪服なので、1着は持っておくと便利です。
略喪服について
準喪服よりも格が下がるのが略喪服で、いわゆる平服を指します。
男性の場合であれば地味な色のダークスーツ、女性であれば地味な色のスーツやワンピースがこれに当たります。
以前は、通夜に駆け付ける際は、取り急ぎ参列したという意味からも平服で構わないとされていました。
しかし、昨今では準喪服を着用する方が大半で、略喪服を着ている方はあまり見かけません。
三回忌以降の法事やお別れ会の際に、主催者側から「平服でお越しください」とアナウンスがある場合にのみ、略喪服を着用すると考えると良いでしょう。
喪服を着こなすポイント
喪服を正しく着こなすにはどのような点に気を付けるべきでしょうか。
喪服を着こなすポイントについて、性別や年齢別に以下でご紹介します。
弔事に出かける前に確認してみると、思わぬ服装のミスを予防できるかもしれません。
男性編
基本的に全身黒のアイテムで揃え、なるべく光沢のない物を選びます。アイテムごとのポイントは下記のとおりです。
・喪服について
準喪服であるブラックスーツの着用が最も一般的です。スーツの生地は黒で光沢の無いものを選びましょう。
・ワイシャツについて
白無地のものを選びましょう。ボタンダウンや色や柄の付いたシャツは避けましょう。
・ベルトについて
黒無地でなるべくシンプルなデザインのものが無難です。バックルが目立つものやヘビ柄のベルトは着用しません。
・ネクタイについて
黒無地のものを選びましょう。ここでも光沢がある素材は好ましくありません。また、ネクタイを結ぶ際もくぼみを作らないのがマナーです。
・靴下について
黒の無地のものを選びます。柄物や白の靴下は避けましょう。
・靴について
黒の革靴が望ましいでしょう。派手な金属の飾りがついたものや、エナメルやスエード素材の靴は避けましょう。
女性編
女性の場合も、黒色のアイテムを身につける、光沢の素材は避けるなど、基本的な考え方は男性の場合と変わりません。ただしアクセサリーなど女性ならではのアイテムもある下記のポイントに注意しましょう。
・喪服について
男性と同様に、準喪服であるブラックフォーマルを選ぶのが好ましいでしょう。デザインは、露出が多いものは控えます。トップスの袖丈については長袖から5分袖、スカート丈は膝からふくらはぎ丈にしておくと上品に見えます。
・バッグについて
黒の布製が基本です。光沢がある素材は避けて、なるべくシンプルなデザインのものを選びましょう。バッグの大きさは、袱紗や数珠が入るものが良いでしょう。
・アクセサリーについて
イヤリングやネックレスは真珠が一般的です。ここでも派手なデザインのものは避けましょう。
・手袋について
露出を避けるためのアイテムとして活躍します。ネイルをしている場合にも活用できますが、お焼香の際には外すようにしましょう。
・ストッキングについて
黒の薄手のストッキングが定番です。薄さは30デニール以下が基本なので覚えておきましょう。厚手のものや網タイツ、柄物のストッキングは避けましょう。
・靴について
シンプルな黒のパンプスを選びましょう。素材は布か革が好ましく、エナメル素材や高いヒールの靴、素足が見えてしまうミュールはどれも相応しくないため避けましょう。
学生の場合
学生であれば、学生服を着用するようにしましょう。学校によっては服の配色やデザインが少し派手な場合もあり、気にされる方もいるかもしれません。
しかし、学生服は葬儀において正装とされているので、配色やデザインについての心配は不要です。
ただし、学生服の丈を変えるなど、アレンジをして制服を着ている方は、校則に沿った着こなしをするように注意しましょう。
子供や乳幼児の場合
子供の場合は、シンプルなデザインで地味な色合いの服を選ぶようにしましょう。たとえば、白いシャツに黒のズボンやスカートを合わせると無難です。
柄物やキャラクターの入ったデザインは避けましょう。
乳幼児の場合も、できるだけ地味な服を選びます。
持参する小物の注意点
喪服についてはしっかり準備できていても、意外と見落としがちなのが袱紗(ふくさ)や数珠といった小物です。
喪服にもルールがあるように、これらの小物にも選び方のポイントがあります。
ここでは葬儀で必要となる代表的な小物についてご紹介します。
袱紗
香典を包む際は袱紗を使用するのがマナーです。弔事用の袱紗の色は、黒やグレー、紺や緑などの寒色系が好ましいでしょう。
結婚式などの慶事でも袱紗を用いますが、その際は赤やピンク色のものを選びます。
弔事用と慶事用で同じ1つの袱紗を使いたいのであれば、紫色が良いでしょう。
初めての袱紗を買うのであれば、紫色のものであれば汎用性が高くお勧めです。
なお、もしも急な弔事で袱紗がなかった場合、もしくは忘れてしまった場合は、ハンカチで代用することもできます。
袱紗を使うように、右、下、上の順にハンカチを畳み、左開きになるようにして使用しましょう。
数珠
数珠はお焼香の際に必要です。数珠の貸し借りは基本的にタブーなので、各自で数珠を用意するようにしましょう。
数珠は宗派によって決まりがあるため注意が必要ですが、迷う場合は略式数珠がお勧めです。
略式数珠は片手念珠とも呼ばれ、1重の数珠を指します。宗派を問わずに全ての宗派で使用できるので、一つ持っておくと安心です。
ハンカチ
ハンカチは手を拭いたり涙をぬぐったりする際に使用する必需品です。
喪服のルールと似ていますが、色は黒もしくは白を選びましょう。
特に女性の場合は、食事の際にハンカチを膝に広げたりすることもあるので、その際は黒色を選ぶと目立ちません。
現在は、昔ほどマナーも厳しくないので、派手なものでなければ許容される風潮でもありますが、マナー違反とされる色は原色で、特にピンクや赤、緑は避けましょう。
基本的に派手な色は好ましくありません。
お通夜は平服でも問題ない
お通夜は本来、平服で参列しても問題ありませんでした。
実際に参列されている方の大半が喪服を着用しているため、周りの目が気になるかもしれませんが、マナーとしては平服でも構わないのです。
平服もないようであれば、私服や作業着でも駆け付けることに意味があるでしょう。
故人との関係性にもありますが、一番大切なのは故人に対して弔意を示すことです。できれば腕に喪章を付けるなど工夫をして参列するようとなお良いでしょう。
葬儀や告別式では喪服を着用しよう
一方で、葬儀や告別式に関しては喪服を着用するのがマナーです。通夜に比べて訃報を受けてから時間があるため、基本的には喪服の準備も間に合うはずです。
たとえ手元にあったとしても高をくくらず、事前に一度袖を通してみましょう。
久しぶりに喪服を着てみたら体型が変わっていて入らなかったという事態もあり得ます。
もしもこのようなトラブルがあったらレンタルサービスを利用したり、量販店で購入したりすることも可能です。
または、友人や同僚に喪服を借りられないか聞いてみるのも良いでしょう。サイズが合わないと不格好になってしまうため注意が必要ですが、出費をせずに場をしのぐことができます。
喪服がない場合の対応方法
急な弔事の場合など、手元に喪服がない場合もあるでしょう。そんな時の対応方法について最後にご紹介します。
まとめ
今回は葬儀で必要な喪服について詳しくご紹介しました。
葬儀において大切なのは、亡くなられた方や遺族の方に弔意を示すことですが、その上で服装は重要です。
どうしても準備が間に合わない場合は仕方がないですが、できる限り相応しい喪服を着用することをお勧めします。
急に必要となる場合が多いので、この記事を参考に事前に準備しておけると良いですね。






















 葬儀・お葬式
葬儀・お葬式 参列マナー
参列マナー 葬儀後
葬儀後 法事・法要
法事・法要 終活
終活 葬儀前(事前相談)
葬儀前(事前相談)