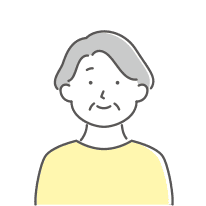末期の水とは
末期の水(まつごのみず)とは、最期を迎える直前や最期を迎えた直後の方の口元を水で湿らす儀式のことです。従来は亡くなる直前に行われていましたが、近年は亡くなった後に行うことの方が多いようです。
故人の口元を水で湿らす行為を「死に水をとる」あるいは「末期の水をとる」と言うこともあります。
末期の水をとるための準備は葬儀社に相談しましょう。故人が病院で最期を迎えた際は、遺族の代わりに医師や看護師が行ってくれる場合もあります。
末期の水の実施手順
末期の水には決まった手順があります。また、末期の水をとる方の順番にも決まりがあります。
ルールやマナーを守って、故人を丁寧に送り出しましょう。
基本的な流れ
末期の水をとる際の基本的な流れは以下の通りです。
1. 箸先に脱脂綿を巻き、白糸で縛って固定します。脱脂綿の代わりに、菊の葉や樒(しきみ)、鳥の羽などを用いることもあります。また、箸の代わりにおろしたばかりの筆を用いることもあります。
2. 桶やお椀に水をくみ、脱脂綿をつけて湿らせます。
3. 湿らせた脱脂綿を上唇から下唇の順番で唇を左から右へ優しくなぞるように当て、故人の唇を湿らせます。
4. 最後に故人の顔を拭きます。おでこ、鼻、顎の順番で丁寧に優しく拭いていきます。おでこやあごは左から右に、鼻は上から下に拭きます。また、顔を拭きながら「お疲れ様」と生を全うした故人を労わる気持ちを込めて声をかけながら行います。
末期の水を行う順番
末期の水は、故人との血縁が濃い方から順番にとります。配偶者あるいは喪主、故人の子、故人の親、故人の兄弟や姉妹、故人の子の配偶者、故人の孫、従兄弟・従姉妹、叔父や叔母、その他の親族、という順番が一般的です。
とはいえ、幼い子どもにまで末期の水をとらせる必要はありません。
病院の医師や葬儀社のスタッフから指示があれば、そちらに合わせてもいいでしょう。
地域や宗派で作法は変わるか
末期の水は、地域や宗派によって作法が異なります。例えば、仏教の儀式とはいえ、亡くなるとすぐに成仏し、あの世で苦しむという考えがない「浄土真宗」では末期の水はとりません。
また、死を安息と考えるキリスト教でも、他の儀式が行われるため末期の水は行いません。一方、天照大神(あまてらすおおかみ)を始めとする神々を祀る「神道(しんとう)」では末期の水を行いますが、その作法が異なります。
神道では死を穢れとするため、清めるために箸ではなく榊(さかき)の葉を用います。
宗派だけでなく、地域や家庭によって作法や手順が異なる場合もあるため、親族や葬儀社に確認することを推奨します。
末期の水に際して気を付けたいこと
末期の水をとる際は、いくつかのポイントに注意が必要です。まず、末期の水は故人の最期を看取った方々が1回ずつ行いましょう。
同じ方が複数回行うのは好ましくないため、気持ちがあっても控える必要があります。また、末期の水は厳かな儀式のため、故人の口の中に無理やり水を入れるようなことは避け、湿らせた脱脂綿や筆で優しく唇の表面を湿らす程度にします。
さらに、末期の水は故人の最期を看取った方全員が参加する儀式であるため、家族が全員揃ってから儀式を行います。故人の意向で自宅にて儀式を行う場合は、冷暖房にも配慮しましょう。
遺体は低温に保たなくてはならないため、高温多湿の夏や暖房を入れる冬は特に注意する必要があります。
末期の水という言葉の由来
末期の水という言葉の由来はお釈迦様の入滅です。入滅とは、お釈迦様の死を意味します。
お釈迦様は、亡くなる間際に口の渇きを訴えて水を求めました。その際に、雪山に住む信心深い鬼神が浄水をお釈迦様に捧げ、そのおかげでお釈迦様は喉を潤して心安らかに入滅することができました。
この逸話が語り継がれ、亡くなる前に喉を潤してから安らかに旅立てるようにという思いを込めて末期の水が行われるようになりました。
一説には、息を吹き返してくれるかもしれないという一縷の希望を抱いて水を飲ませる、というものもあります。
また、仏教の教えでは、死後の世界では食事や水を摂ることができなくなると考えられているため、水を飲ませて喉を潤してから冥土に送り出すという意味もあります。
まとめ
末期の水の意味から、実施手順、地域や宗派によって作法が異なること、末期の水に際して気を付けたいこと、そして末期の水の由来までを解説しました。末期の水は、故人が心安らかに旅立てるようにするための大切な儀式です。
末期の水の意味を理解した上で、いざという時も落ち着いて執り行えるようにしておきましょう。



















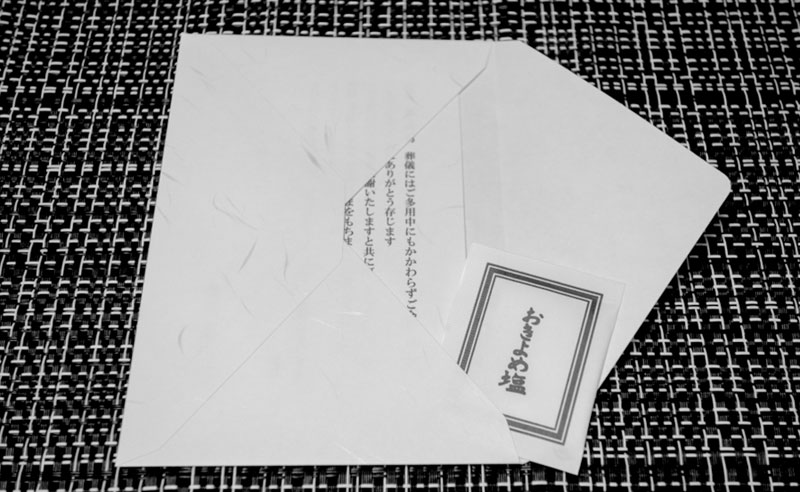


 葬儀・お葬式
葬儀・お葬式 参列マナー
参列マナー 葬儀後
葬儀後 法事・法要
法事・法要 終活
終活 葬儀前(事前相談)
葬儀前(事前相談)